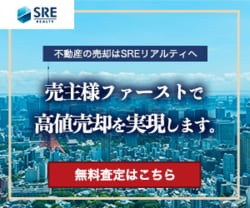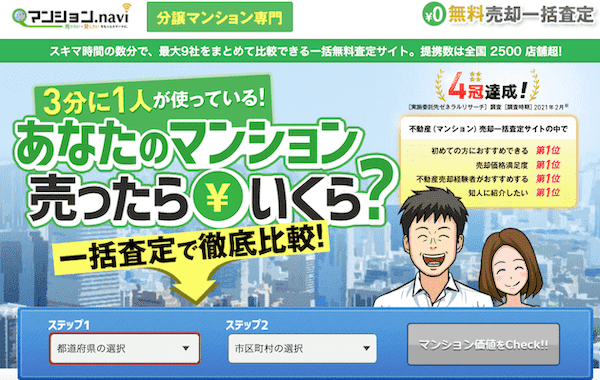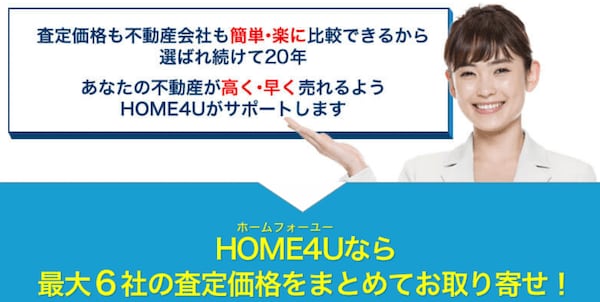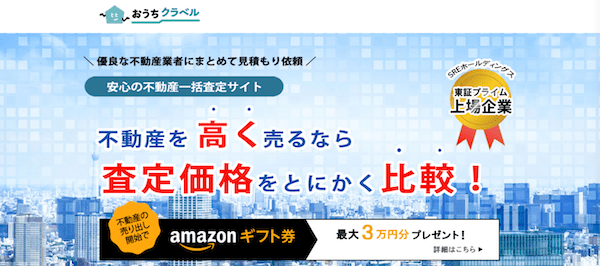「所有者不明土地」とは、文字通り「誰が持っているのか分からない土地」のことですが、なかでも相続に絡む所有者不明土地が多いことから、「相続時の登記を義務化すること」が検討されています。今回は、行政が進めている対策について詳しく解説します。(ファイナンシャルプランナー・佐藤益弘)
【※前回の記事はこちら!】>>最近よく耳にする「所有者不明土地」とは?
「所有者不明土地」について
今後、予想される問題とは
わが国の人口ピラミッドを見たときの最大の多数派である団塊の世代といわれる方たちが、後期高齢者である75歳を迎えるのが2025年前後です。一般的に後期高齢者になると、痴呆症の発症や要介護になる確率が高くなり、意思表示がしづらい状況に陥りがちです。
そして、超高齢社会が進展する中、相続も増加することが予想され、2030年前後に多死社会・大量相続時代が訪れるといわれています。
【※関連記事はこちら!】>>「相続」で必要な書類、手続きのスケジュールを解説!
相続の連鎖によって「所有者不明土地」が、より大量に発生する可能性が高くなりますから、この問題の解決が喫緊の課題になっています。
一つの「所有者不明土地」を解決するためには、所有者の探索をすることになります。そのためには多大な時間と費用が必要になります。「所有者不明土地」が大量に発生すれば、事態の深刻化が避けられそうにありません。
先行して改正された「土地基本法」が
2020年4月1日施行に
2020年4月、土地の利用や活用に関する指針を示した「土地基本法」が30年ぶりに改正され、「所有者不明土地」問題の解決に向けた事実上のキックオフとなりました。
土地基本法はバブル経済真っ最中の1989年(平成元年)にできた法律でしたから、土地活用を促進することを前提に、土地所有者の“権利”が中心的に示されていました。
それが2020年(令和2年)に改正された土地基本法では、「所有者不明土地」問題における、管理不全になっている土地を解消するために、土地所有者の”権利”だけでなく、“責務(責任と義務)”も示されることになりました。

どういうことかというと、わが国の所有権はとても強い権利で、たとえ隣近所の土地が管理不全になって迷惑を掛けていても、所有者に無断で活用したり、立ち入ったりすることができないことになっています。
しかし、このような土地をそのまま放置すると、近隣住民が多大な迷惑を被り、ひいてはその地域全体の資産価値を下げてしまうような状態に陥ってしまうかもしれません。
こうした問題の解決のためには……
・所有者が土地の利用・管理について第一次的な”責務”を負う
・所有者による土地の利用・管理が困難な場合には、近隣住民や地域コミュニティ等が行う利用・管理には公益性があると考えられ、そのために所有権は制限され得る
・国や地方公共団体は、利用・管理の促進策やその法的障害の解消のための施策を講じるべきである
といったことが必要で、今回の改正に盛り込まれています。
そうすることにより、管理不全の陥っている空き家や空き地に対応していこうとしているわけです。
「所有者不明土地」問題の解決に向けた
これまでの国の動き
これまで「所有者不明土地」問題に対して、さまざまな議論が行われてきました。
たとえば、2018年(平成30年)に「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」(所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議)が決まり、法務省や国土交通省など関係省庁で「人口減少社会における土地に関する基本制度の在り方」等について検討を進めています。
そして、同年11月に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行されました。
内容としては、登記名義人として記載されている所有者が死んだ後、長期間にわたって登記されていない土地があった場合、登記官が職権を用いて、亡くなった所有者の法定相続人を探した上で「長い間、相続登記未了であること」などを登記に付記して、法定相続人に登記手続きを直接促すことができるようになりました。
ただ、「所有者不明土地」問題を解消するためには、まだまだ必要なことが山ほどあります。
問題解決をより一層進めるため、2019年(平成31年)3月より法務省にて法制審議会-民法・不動産登記法部会が立ち上がり、議論を経て2019年12月3日に「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」として公表されました。パブリックコメントを受けて、2020年夏頃までには最終試案が出され、秋の臨時国会での法案成立を目指すことになっています。
民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の
改正法案のポイントは?
「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」 の中身を覗いてみましょう。
まず、「所有者不明土地」問題の根本的な原因である「相続等による所有者不明土地」の”発生を予防”するための仕組みづくりとして、不動産登記情報の更新を図る、としています。
具体的には「相続時の登記を義務化すること」を挙げています。
また、「所有者不明土地」の”発生を抑制”するため、「土地所有権の放棄」や、遺産分割を10年以内に行うなど「期間制限の設定」などが検討されています。
そして、「所有者不明土地」を”円滑かつ適正に利用”するための仕組みづくりとして、「共有関係にある『所有者不明土地』を利用できるようにする方策」が考えられています。
具体的には、共有を解消しやすくするための、民法の共有制度の見直しです。この件は2021年度の「住生活基本計画」でも、「老朽化マンション」が主な議題に上がっていることから、改正が求められています。
また、所有者不明土地の管理を合理化するために、現行法にはない「特定の財産のみを管理する制度」が検討されています。このほか、近隣の土地の所有者が境界の確定や確認などをする際に「所有者不明土地」を利用しやすくするためのルール改正も提言されています。
【関連記事はこちら】>>「権利未登記」「違法建築」「境界未確定」など”不動産の売却”でよくあるトラブルの解決法とは?
まとめると……
-
1.相続等による所有者不明土地の発生を予防するため「相続登記の義務化」を進め、不動産登記情報の更新を図る
-
2.相続等による所有者不明土地の発生を抑制するため「土地所有権の放棄」や「遺産分割の期間制限」などを設ける -
3.所有者不明土地の利用について円滑化かつ適正化を図る
・所有者不明土地の共有制度を見直す
・所有者不明土地の財産管理制度を見直す
・所有者不明土地を近隣地の住民が使えるように「相隣関係規定」を見直す
以上の事柄は、執筆時点(2020年4月)では現在進行形の話なので、変更されることも予想されます。
なぜなら、改正される法律は、民法(物権法、相続法)及び不動産登記法など非常に多岐にわたります。また、改正されると、その後の生活に大きなインパクトを持つことになるからです。
次回からは、「所有者不明土地」の具体的な5つのケースについて、お伝えします。
|
「所有者不明土地」シリーズのリンク集 |
|
◆概要編◆ 2.「所有者不明土地」関連の法改正の行方は?
◆ケース別解決策◆ 4.「相続登記」をして土地の名義変更をしたい
|
AI査定×エージェント制「SREリアルティ」の不動産査定
SREリアルティは、東証プライム上場のソニーグループ関連会社が運営する不動産仲介会社で、売却専門エージェントが担当する「片手仲介」が特徴です。売主に寄り添うサポート力に強みがあり、顧客満足度93%と高い評価を得ています。ソニーグループと共同開発したAI技術を査定にも活用。高値売却を目指したい方におすすめです。(※対応エリア:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都府)
※不動産一括査定サイトでは、売却したい不動産の情報などを入力すれば、無料で複数社に査定依頼ができます。査定額を比較できるので売却相場が分かり、きちんと売却してくれる不動産会社を見つけやすくなる便利なサービスです。
| ◆SUUMO(スーモ)売却査定 | |
|
無料査定はこちら >> |
|
| 特徴 | ・圧倒的な知名度を誇るSUUMOによる一括査定サービス ・主要大手不動産会社から地元に強い不動産会社まで2000社以上が登録 |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地 |
| 紹介会社数 | 10社(主要一括査定サイトで最多)※査定可能会社数は物件所在地によって異なります |
| 運営会社 | 株式会社リクルート(東証プライム) |
|
|
|
| ◆すまいValue | |
|
|
|
| 特徴 | ・大手不動産会社6社が運営する一括査定サイト |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション、一棟アパート、一棟ビル |
| 対応エリア | 北海道、宮城、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、愛知、岐阜、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、岡山、広島、福岡、佐賀 |
| 運営会社 | 大手不動産会社6社(東急不動産、住友不動産ステップ、三井のリハウス、三菱地所の住まいリレー、野村の仲介+、小田急不動産) |
|
|
|
| ◆マンションナビ | |
|
無料査定はこちら >> |
|
| 特徴 |
・マンションの売却に特化 |
|---|---|
| 対応物件 | マンション |
| 紹介会社数 | 最大9社(売却・買取6社、賃貸3社) |
| 運営会社 | マンションリサーチ |
|
|
|
| ◆HOME4U(ホームフォーユー) | |
|
無料査定はこちら >> |
|
| 特徴 | ・悪質な不動産会社はパトロールにより排除している ・20年以上の運営歴があり信頼性が高い ・2500社の登録会社から最大6社の査定が無料で受け取れる |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、ビル、アパート、店舗・事務所 |
| 紹介会社数 | 最大6社 |
| 運営会社 | NTTデータ・ウィズ(東証プライム子会社) |
|
|
|
| ◆リビンマッチ | |
| 特徴 |
・マンション、戸建、土地のほか、工場、倉庫、農地の査定にも対応可能 ・1700社の不動産会社と提携 |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫 |
| 紹介会社数 | 最大6社(売却6社、賃貸、買取) |
| 運営会社 | リビン・テクノロジーズ(東証グロース上場企業) |
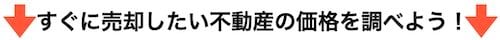
| ◆いえカツLIFE | |
|
無料査定はこちら >> |
|
| 特徴 |
・対応可能な不動産の種類がトップクラス |
|---|---|
| 対応物件 | 分譲マンション、一戸建て、土地、一棟アパート・マンション・ビル、投資マンション、区分所有ビル(1室)、店舗、工場、倉庫、農地、再建築不可物件、借地権、底地権 |
| 紹介会社数 | 最大6社(売買2社、買取2社、リースバック2社) |
| 運営会社 | サムライ・アドウェイズ(上場子会社) |
|
|
|
| ◆おうちクラベル | |
|
無料査定はこちら >> |
|
| 特徴 |
・AI査定で、査定依頼後すぐに結果が分かる |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション、一棟アパート |
| 紹介会社数 | 最大9社 |
| 運営会社 | SREホールディングス株式会社(東証プライム上場企業) |
|
|
|
| ◆イエウール | |
|
無料査定はこちら >> |
|
| 特徴 |
・掲載企業一覧を掲載、各社のアピールポイントも閲覧可能 |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地 |
| 紹介会社数 | 最大6社 |
| 運営会社 | Speee |
|
|
|
| ◆LIFULL HOME'S(ライフルホームズ) | |
|
無料査定はこちら >> |
|
| 特徴 |
・日本最大級の不動産ポータルサイト「LIFULL HOME'S」が運営 |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、倉庫・工場、投資用物件 |
| 紹介会社数 | 最大6社 |
| 運営会社 | LIFULL(東証プライム) |
|
|
|
不動産一括査定サイト10社を比較
| サイトロゴ |  |
 |
 |
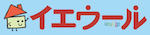 |
 |
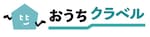 |
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス名 | suumo売却査定 | すまいValue | HOME4U | イエウール | ライフルホームズ | おうちクラベル | イエイ | マンションナビ | リビンマッチ | いえカツLIFE |
| ポイント | 知名度の高いスーモで、大手から地元の会社まで様々な不動産会社に査定を依頼できる。当社調査で満足度No.1 | 大手不動産仲介6社の共同運営で、査定が可能。都市圏の物件に強い。大手の査定結果を比較するのに便利。 | NTTデータの子会社が運営。20年以上の運営歴で安心感がある。大手のほか、店舗や事務所の査定にも対応。 | 都市圏だけでなく、地方の不動産会社も提携多数。対応する物件タイプが豊富で、農地の査定にも対応している。 | 匿名でも査定が可能。提携社数が多く、投資用物件の査定にも対応。東証プライム上場。当社調査で満足度No.2 | 東証プライム上場企業が運営。AI査定ですぐに結果が分かる。売り出し開始でAmazonギフト券最大3万円プレゼント。 | 仲介営業のお断り代行サービスが特徴。査定から成約まで完了でAmazonギフト券最大10万円贈呈。東証プライム上場企業が運営。 | マンションに特化。売却・賃貸、両方の査定が分かる。マンション売買の分析データに詳しい。マンション査定なら選択肢に入れたい。 | 都市部だけでなく、地方の不動産会社とのネットワークが充実。幅広いエリアで査定対応している。20年の運営実績あり。 | 急ぎの売却や訳あり物件の査定に強み。3つの売却方法(仲介、買取、リースバック)を選べる。 |
| ユーザー満足度※ | 3.8 ★★★★★ |
3.4 ★★★★★ |
3.4 ★★★★★ |
3.3 ★★★★★ |
3.6 ★★★★★ |
3.1 ★★★★★ |
3.6 ★★★★★ |
2.8 ★★★★★ |
3.2 ★★★★★ |
ー |
| 提携社数 | 2000以上 | 大手6社 (住友不動産ステップ、東急リバブル、三井のリハウス、野村の仲介など) |
2500以上 | 2600以上 | 4900以上 |
1500 |
1700以上 | 2500 | 1700以上 | 500 |
| 最大紹介社数 | 10社 ※物件所在地によって異なる |
6社 | 6社 | 9社 | 6社 |
9社 |
7社 | 9社 (売却6社、賃貸3社) |
6社 | 6社 (仲介2社、買取2社、リースバック2社) |
| 主な対応物件 | マンション、戸建て、土地 | マンション、戸建て、土地 | マンション、戸建て、土地、ビル一室、店舗・事務所・倉庫、マンション一棟、アパート一棟、ビル一棟 | マンション、戸建て、土地、ビル一室、店舗・事務所・倉庫、マンション一棟、アパート一棟、ビル一棟、区分マンション(収益)、区分ビル(ビル一室)、農地 | マンション、戸建て、土地、マンション一棟、アパート一棟、ビル一棟、倉庫・工場 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション・アパート、店舗、事務所 | マンション、戸建て、土地 | マンション | マンション、戸建て、土地、一棟アパート・一棟マンション、投資マンション(1R・1K)、一棟ビル/区分所有ビル(ビル1室)、店舗・工場・倉庫、農地、その他 | マンション、戸建て、土地、再建築不可物件、借地権、底地権、その他(共有持分も査定・売却対象)など |
| 対応エリア | 全国 | 全国(一部を除く) | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 東京・神奈川・千葉・埼玉 |
| 解説記事 | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら |
| 公式サイト | 詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
※ユーザー満足度は、ダイヤモンド不動産研究所が独自にアンケート調査した結果をもとに算定。詳しい記事はこちら
|
【不動産仲介会社の評判を徹底調査!】 |