住宅ローンの変動金利が10年後どのくらい上昇するのかを予想します。実は、各銀行はさまざまな固定期間の金利を設定しており、その数値から変動金利が将来どうなると予測しているのかが計算できるのです。そこで主要12銀行の変動金利が10年後、20年後にはどこまで上がるのかを試算しました。(住宅ローンアドバイザー・淡河範明)
住宅ローンの10年後の変動金利を試算する方法とは
住宅ローンの金利は、市場の金利や日銀の金融政策を参考にしつつ、銀行の経営方針に応じて設定してきたと考えられます。
現在の金利上昇の過渡期において、銀行の金利決定を行う担当者は金利を何%にすればよいか日夜悩んでいるに違いありません。
そこで注目されるのが、住宅ローンの店頭金利です。店頭金利は、固定期間ごとに景気の先行きや金融政策の変化を織り込みつつ、自行の経営スタンスを反映して設定されていると考えられるからです。
つまり、店頭金利を分析することで、それぞれの銀行の先行きの見通しを計算できます。
これは、「インプライド・フォワードレート」と呼ばれるもので、「長期の固定金利が複数設定されていれば、将来の金利が推計できる」という考え方です。
計算方法を解説しましょう。まずは金融商品AとBについて次のような運用があるものとして、例にとってみます。
- A:1年物、金利年1%→100円分購入で、1年後に101円
- B:2年物、金利年2%→100円分購入で、2年後に約104円
もし、Aを1年後に再び年利1%で運用すると結果は以下となります。
- A:2年後に102円
B:2年後に約104円
したがって、1年後の金利が確実に1%と分かっていれば誰もAは選ばないでしょう。次に、1年後の金利が年利3%の商品Cがある場合を考えます。
Bを買う:2年後に約104円
この場合、商品A+C、商品Bのどちらを買っても有利・不利というような状態にはなりません。つまり、1年後の1年金利について、約3%のリターンが期待できると考えているから、商品Aは成立しているのです。
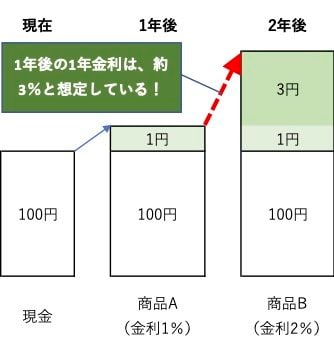
もし、どちらかがより儲かると予想する人がいれば、そちらが買われます。買い手が増えれば利回りは下がり、どこかで落ち着くはずです。取引がたくさん行われてAとBの利回りが落ち着いたら、「将来の金利について合意が形成された」と考えるのです。
つまり、1年と2年の金利があれば、1年後の1年金利の予測ができるのです。この考え方に基づいて将来の変動金利を予想しましょう。なお変動金利は、「半年ごとに金利を見直す」という商品なので、半年固定金利と考えて試算します。
-
【試算の前提】
-
主要な12銀行について、インプライド・フォワードレートを計算してみました。銀行は、以下の銀行です。
・大手銀行=みずほ銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ銀行
・ネット銀行など=イオン銀行、SBI新生銀行、住信SBIネット銀行、ソニー銀行、楽天銀行、りそな銀行、auじぶん銀行、PayPay銀行
今回は、銀行ごとに金利がどのように推移すると予測しているかを把握するため、各行のサイトに掲載されている固定期間別の店頭基準金利(2025年4月現在)をもとに、変動金利(基準)のインプライド・フォワードレートを計算します。変動金利(基準金利)を算出したら、それぞれの銀行の「金利優遇幅」を差し引いて、変動金利(適用金利)を算出します。
※全期間固定は除いて計算。なお、市場金利を用いてインプライド・フォワードレートを計算すると、市場関係者の予測を把握できます。また、本来は期間リスクプレミアムを控除して計算しますが、現在の金利水準から低いため期間リスクプレミアムがきわめて小さいことから、ここでは無視して計算しています。
住宅ローン10年後の変動金利を試算した結果(2025年4月)
まずは、12銀行の10年後の変動金利を試算してみましょう。各銀行が発表している固定金利から試算すると以下のようになりました。試算の結果は、絶対的なものではなく、あくまでも参考値だと思ってください。
| 銀行名 | 10年後の変動金利(試算) | |
|---|---|---|
| 三井住友銀行 | 2.892% | |
| 楽天銀行 | 2.636% | |
| 三井住友信託銀行 | 2.580% | |
| りそな銀行 | 2.532% | |
| イオン銀行 | 2.440% | |
| 三菱UFJ銀行 | 2.109% | |
| auじぶん銀行 | 2.002% | |
| みずほ銀行 | 1.926% | |
| ソニー銀行 | 1.866% | |
| PayPay銀行 | 1.668% | |
| SBI新生銀行 | 1.563% | |
| 住信SBIネット銀行 | 1.493% | |
| ※2025年4月の各銀行の金利で試算。あくまでインプライド・フォワードレートの考え方で試算したものであり、10年後の変動金利を確約するものではない | ||
10年後の変動金利を試算した結果、金利が最も低いのは、住信SBIネット銀行の1.493%で、金利が最も高いのは、三井住友銀行の2.892%。12銀行の平均値は2.142%です。
2025年1月に日銀の再利上げによって政策金利が0.25%引き上げられ、4月時点で0.5%となっています。
半年前の調査では10年後の変動金利の平均値が1.618%でした。今回は約0.543%上昇し、12行すべてが金利を引き上げました。
政策金利は0.25%程度の上昇でしたが、10年後の変動金利が0.543%も上昇したのは、調査したすべての銀行が「10年後の金利は上昇する」ということが共通認識になったと推測できます。
金利の先高感を銀行が意識している
実際の固定期間ごとの店頭金利は、すべての固定期間の金利が上昇しました。
前回の調査との違いとしては、固定期間が短い金利タイプの上昇より、固定期間の長い金利タイプの伸びがやや上回っていることです。これは、金利の先高感を銀行が意識しているからではないかと考えます。
また特徴的なのは、12銀行中、9行が10年固定金利の適用金利よりも、10年後の変動金利が高く設定されていることです。
前回の調査では銀行の営業戦略の変化を予想しましたが、実際に銀行の住宅ローンの取り組み方針に大きな変化が生まれてきたようです。
住宅ローンの変動金利の基準金利の変化だけでなく、調査した銀行の半数を超える7行が優遇金利を変更。そのうち5行は、基準金利の上昇を緩和するために優遇幅を拡大しています。おそらく、取引減少を嫌がってのことだと思われます。
残り2行は、金利優遇幅を縮小しました。住宅ローンによる収益性を健全な状態に戻そうとするものだと思われます。これは、正常な動きだと考えています。
銀行も今後は横並びではなく、それぞれの戦略にのっとって動いていくことが予想されるため、住宅ローンはより慎重に選ぶ必要があるでしょう。
| 住宅ローン実質金利ランキング[新規借入] |
10年後、20年後、30〜35年後までの変動金利推移を銀行ごとに予測
それでは各銀行の「X年後の変動金利推移」を試算していきます。
銀行により固定金利の最長固定期間が、10年、20年、30年または35年と3パターンあるので、3つに分けてグラフを作成してみました。
今後20年までの金利推移予測(三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、ソニー銀行、SBI新生銀行、三井住友銀行)
今後30年or35年までの金利推移予測(三井住友信託銀行、住信SBIネット銀行、auじぶん銀行、PayPay銀行)
10年後までの金利推移予測
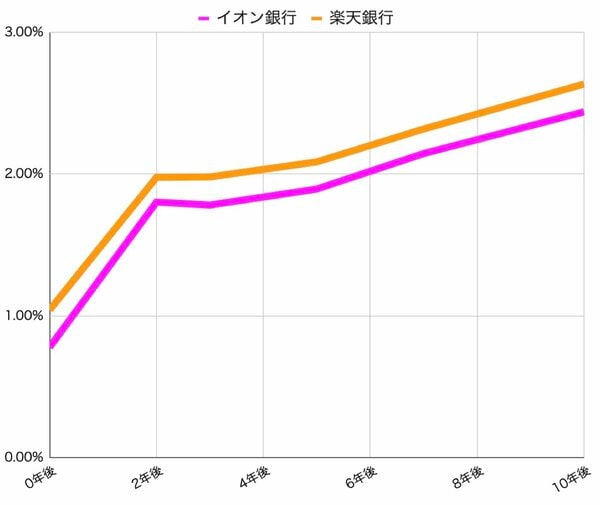
イオン銀行と楽天銀行は、金利上昇のペースが前回調査より約0.5%上昇する見込みと予想しているようです。
具体的には、2年以内に金利が2%程度まで上昇し、10年前後の2.5%程度まで緩やかに上昇するという予想です。
20年後までの金利推移予測
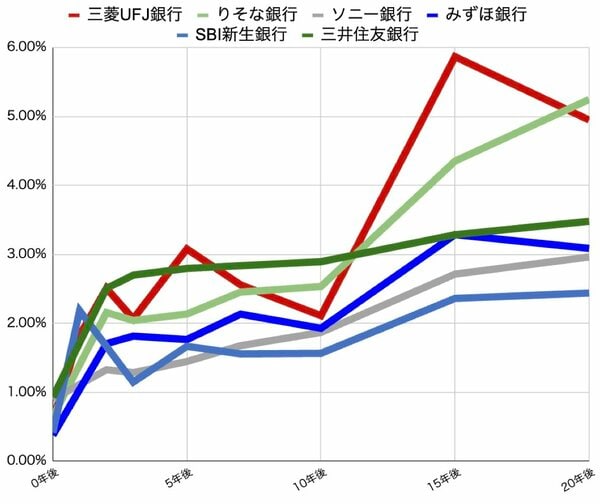
三菱UFJ銀行
1年以内に変動金利が2%を超えると見込んでいるようです。その後、5年以内に3%近くまで上昇。その後は、金利が低下し10年後から金利の再上昇が始まるといった循環型の金利推移を予測しているようです。ある程度オーソドックスな予測のように思われます。
ただ、4月の変動金利は0.595%と適用金利を据え置いたので、将来の金利上昇を前提に、戦略的に変動金利の顧客の囲い込みを続けていると考えられます。
みずほ銀行
変動金利1%には1年以内に達すると予測してはいるものの、金利上昇は緩やかになると想定しており、変動金利が2%を超えるのは7年後と想定しているようです。その後、金利は徐々に上昇していきますが、20年後の変動金利は3%程度までと緩やかながら安定的な成長を見込んでいるようです。
三井住友銀行
当初の金利上昇スピードが速いと考えているようで、2年で2%の上昇を見込んでいます。ただ、その後は好況局面が終了し、10年後に3%まで緩やかに上昇すると予測しているようです。
りそな銀行
2年以内に2%になると見ているようですが、その後は金利が伸び悩み、また10年後以降、20年後までに5%を目指して上昇すると見込んでいるようです。
やや不自然なくらいに右肩上がりの金利上昇となっており、10年後以降は営業的な観点から数値を付けにいったにおいがします。
ソニー銀行
10年以内に金利は2%まで届くことはないという、かなり緩やかな金利上昇を予測しているようです。その後も緩やかな金利上昇を見込んでいますが、そこから10年かけて3%程度に上昇すると見ているようです。
SBI新生銀行
これまでの銀行とは大きく異なり、金利が2%になるのは11年目以降と金利上昇が緩やかなシナリオを持っているようです。
なお、SBI新生銀行は1年固定を有する数少ない銀行で、その金利はやや高く設定されているためデータとして異常値として取り扱っています。
今後30年or35年までの金利推移予測
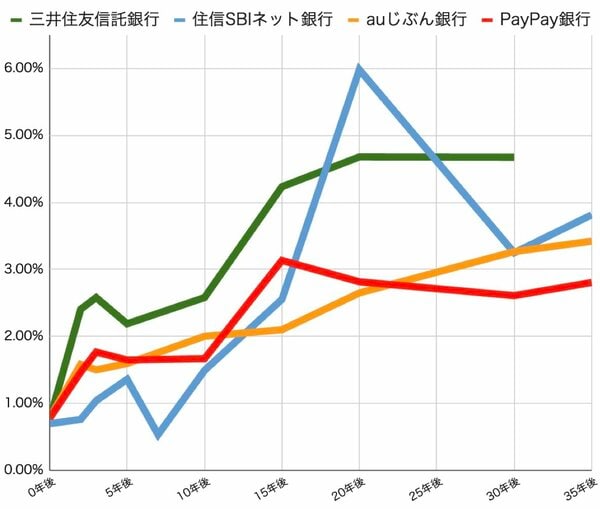
三井住友信託銀行
固定金利の最長固定期間が30年までの三井住友信託銀行の金利は、2年以内に2%まで上昇すると見込んでいるようです。3年たって景気は減速するも徐々に持ち直し、15年後までに変動金利は4%を超えるという予想です。
住信SBIネット銀行
5年かけて徐々に金利が上昇し、3年目でようやく1%に到達、5年後には金利が大きく下落、7年目以降には上昇に転じ、20年目には6%まで上昇すると見込んでいるようです。
おそらくこれは予測ではなく、営業的な金利設定により生じた"ゆがみ"ではないかと思われます。
auじぶん銀行
金利は10年以内に2%になると予想しており、その後、20年くらいかけて3%まで上がるという予想です。
PayPay銀行
金利2%は11年目以降になると見ているようですが、15年目にはいきなり3%近くまで上昇するという非常に大胆は金利設定となっています。おそらく営業政策的な金利設定なのでしょう。
変動金利上昇は想定すべき
以上のように、銀行によって変動金利の見通しはかなり違います。また、繰り返しになりますが、あくまで固定金利との金利差から試算したものであり、確定的な情報ではありません。
とはいえ、主要12銀行は10年後の変動金利が、1.493%〜2.892%になると想定していると試算できることはお分かりいただけたかと思います。
| 住宅ローン実質金利ランキング[新規借入] |
銀行は変動金利が何年以内に1%、2%を超えると予想しているか
各銀行が変動金利の上昇時期をどのように想定しているのか、試算してみましょう。
政策金利0.5%の壁は突破する
2025年1月、日銀の再利上げにより政策金利がとうとう0.5%になりました。2007年に政策金利を0.5%まで引き上げた後、リーマンショックの影響で再び金利を引き下げざるを得なくなった経緯があることから、政策金利は0.5%が一つの壁とみなされています。
日銀は現在の金融緩和の状態から徐々に正常な状態に近づけていく方針を示しているので、年内にあと1、2回の利上げを見込む識者も多数いました。
しかし現在、利上げの前提条件である好景気や賃上げに黄信号がともっています。トランプ関税政策が景気の悪化要因になる恐れが出てきました。
そのため、トランプショックの影響を見極める時間が必要になってくると予想されます。ただし、基本方針は変わっていません。政策金利の引き上げは、将来的に行われる可能性が高いと見ています。
今後は国内景気の動向、賃金動向を見極め、日銀が政策金利を再度引き上げに転じるタイミングに注目すべきです。
1995年以来、30年以上も政策金利が1%を超えていないので、なかなか金利が上昇するというイメージを持てない人も多いかと思いますが、金融緩和の状態を永続させることはないでしょう。
いつ変動金利が上がるのかがわかれば、金利タイプを適切に判断できる
政策金利が0.5%の壁を超えると、おそらく変動金利は1%を超えるようになるでしょう。ただし、1%になったとしてもそれ以上の上昇がなければ変動金利が有利となります。
もし、変動金利が早期に2%を超えるようであれば、固定金利を選択したほうが有利になる可能性が高くなります。
つまり、いつ変動金利が上がるのかがわかれば、金利タイプを適切に判断できるというわけです。
以下は、主要12銀行が何年以内に変動金利が1%、2%を超えると予想しているのかを試算した結果です。
| 時期 | 銀行名 |
|---|---|
| 1年以内 | みずほ銀行、三菱U F J銀行、三井住友銀行、ソニー銀行、auじぶん銀行、りそな銀行、イオン銀行、SBI新生銀行、楽天銀行、PayPay銀行 |
| 2年以内 | ー |
| 3年以内 | 住信SBIネット銀行 |
| 4年以内 | ー |
試算の結果、変動金利が1%を超える時期はほぼ1年以内と考えている銀行がほとんどでした。前回の試算と比べ、金利上昇のスピードが加速していることを感じます。ただし、住信SBIネット銀行だけが3年目に上がると予想しているようです。
| 時期 | 銀行名 |
|---|---|
| 2年以内 |
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、りそな銀行 |
| 5年以内 | 楽天銀行 |
| 7年以内 | みずほ銀行、イオン銀行 |
| 10年以内 |
auじぶん銀行 |
| 15年以内 |
ソニー銀行、住信SBIネット銀行、SBI新生銀行、PayPay銀行 |
2%を超える時期は各銀行のスタンスにバラツキがあることがわかります。2年以内と予想しているのはメガバンクや信託銀行が中心で、ネット銀行などは10年後、15年後までは2%を超えないと予想しているようです。
変動金利のメリット・デメリットは?
変動金利のメリットは、10年固定金利や35年固定金利といった、他の金利タイプより金利水準が低いことです。また、現在のような低金利であれば借りられる金額が増えるので、不動産が高騰しているときには、有力な選択肢になります。
一方、金利が上昇すると、当然ながら支払わなければならない利息が増え、毎月返済額が増加するので家計を圧迫するというデメリットもあります。
実際には、大半の銀行のルールとして変動金利は半年に一度(4月と10月)、その時点の市場金利に合わせて見直され、3カ月後(7月と翌年1月)から適用されます。
ただし、あまりにも金利上昇が急激な場合に備えて、激変緩和措置が用意されています。以下の2つがその激変緩和措置です。
(1)毎月の返済額は5年間変更しない
(2)返済額の引き上げは、1回につき1.25倍が上限
こうした激変緩和措置を用意しているものの、金利が大きく上昇した場合は、結果的に総返済額が膨らんでしまうため、支払いに困ってしまう人も出てきます。
変動金利VS固定金利、どちらを選ぶべきか
住宅ローンを選択する際、変動金利と固定金利のどちらを選ぶかは悩ましい問題です。
変動金利は今のところ低金利ですが、将来的に金利が上昇するリスクがあります。一方、固定金利は変動金利より金利が高く設定されていますが、返済期間中は金利が変わることはありません。
結論から言えば、金利の動向を正確に予測することはできないため、どちらのタイプがより有利になるか断定することはできません。
変動金利か固定金利かを選ぶ際に重要なのは、自分の家計状況に合わせて、適切な金利タイプを選ぶことです。家族構成や収入、支出、将来の教育費や老後資金など、様々な要因を考慮する必要があります。許容できるリスクの範囲内で、毎月の返済額が最小となる金利タイプを選ぶべきでしょう。
具体的には、まず毎月の支払い可能額の上限を決めます。次に、変動金利、固定金利で、毎月の返済額をシミュレーションします。最終的に、将来にわたって支払いが可能な金利タイプの中から、最適なものを選択することが賢明です。
このように自分の状況に合った金利タイプを選ぶことで、金利リスクを回避し、家計を守ることができるはずです。
【関連記事】>>【最新】住宅ローン変動金利ランキング132行比較|今後の金利上昇を見越して固定を選ぶべき?
変動金利が上昇したケースをシミュレーション
では、変動金利が上昇した場合、毎月の返済額がどれくらい増加するのか、シミュレーションしてみましょう。日本では、ここ10年近く、超低金利状態が続いており、変動金利の住宅ローン金利も低いままです。
しかし、過去には変動金利が8%を超えていたこともあるため、金利上昇のリスクはゼロではありません。そこで、金利が上昇する2ケースをシミュレーションしてみました。
まず最初に確認したいのが、変動金利が1%で変化しないケースの場合は、毎月返済額は8.5万円で一定です。
1年目〜 1%
11年目〜 2%
21年目〜 3%
31年目〜 4%
【毎月支払額の推移】
当初〜 8.5万円
11年目〜 9.5万円
21年目〜 10.2万円
31年目〜 10.5万円
このように、当初と比べると、およそ2万円も増加します。
借入額や借入期間によって毎月返済額は変わってきます。例えば期間35年で、借入額が2倍の6000万円だったとすると、毎月返済額はこの2倍になるので、およそ4万円も毎月返済額が増加することになります。
1年目〜 1%
11年目〜 3%
21年目〜 5%
31年目〜 7%
【毎月支払額の推移】
当初〜 8.5万円
11年目〜 10.6万円
16年目〜 10.7万円
21年目〜 12.2万円
31年目〜 12.8万円
このケースは、31年後には金利が7%に到達するが、過去の金利上昇から考えれば、あながち高すぎる金利ではありません。
毎月支払額は当初8.5万円で一緒ですが、31年目は12.8万円となります。変動金利が変化しなかったケースに比べて毎月支払額は4.3万円アップします。およそ1.5倍です。家計にとって相当大きな痛手となります。
変動金利のリスクを抑える3つの方法
この変動金利の金利上昇リスクにどう対応すればいいのでしょうか。そこで、以下の3つの方法を考えてみました。
(A)繰上返済(返済額軽減型)を行う
繰上返済には、「返済額軽減型」「期間短縮型」の2つの方式がありますが、まずは、(A)繰上返済(返済額軽減型)でどの程度の効果があるかシミュレーションしてみましょう。
「返済額軽減型」は、返済期間は短縮せずに、繰上返済した分は毎月支払額を減らすことに使うというもの。毎月の支払額をなるべく上げたくないという人に向いています。
先ほどの(1)10年ごとに1%上昇するケースで検証してみます。
繰上返済は毎月の支払いに加えて、返済をすることになるので、家計がギリギリのケースではなかなか対応できません。そこで金利が上昇する前に繰り上げ返済することにしましょう。
当初の10年間について、毎月2万円を家計からひねり出して、年に1回繰上返済します。繰上返済する金額は合計で以下のように240万円です。
2万円✕12カ月✕10年=合計240万円
試算すると、この繰上返済(返済額軽減型)で総支払額が95万円も安くなります。
|
繰上返済(返済額軽減型)の効果を試算 (借入金額3000万円、借入期間35年、変動金利1%から10年ごとに1%アップ。繰上返済は毎年24万円×当初10年) |
||||
| 繰上返済 | 繰上返済 なし |
→ | 繰上返済 (返済額軽減型) |
|
|---|---|---|---|---|
| 返済期間 | 35年 | → | 35年 | |
| 毎月返済額 | 1年~/8.5万円 11年~/9.5万円 21年~/10.2万円 31年~/10.5万円 |
→ | 1年〜/8.5万円 11年~/8.5万円 21年~/9.1万円 31年~/9.3万円 |
|
| 総支払額 | 4014万円 | → | 3919万円 (-95万円) |
|
もし、金利が上昇しても、毎月支払額はそれほど増加せず、31年目以降の毎月支払額は9.3万円と、当初に比べて0.8万円のアップで済んでいます。この程度なら、家計への負担も小さいといえます。
(B)繰上返済(期間短縮型)を行う
繰上返済(期間短縮型)は、繰上返済したお金を返済期間の短縮に使うというものです。毎月支払額が多少増えてもいいから、とにかく総支払額を少なくしたい、という節約家の人には、「期間短縮型」がおすすめです。
試算した結果は以下のとおりで、総支払額は繰上返済しなかった場合に比べて210万円も少なくなりました。240万円を繰上返済することで、210万円もの効果を生むことができるのです。
|
繰上返済(期間短縮型)の効果を試算 (借入金額3000万円、借入期間35年、変動金利1%から10年ごとに1%アップ。繰上返済は毎年24万円×当初10年) |
||||
| 繰上返済 | 繰上返済 なし |
→ | 繰上返済 (期間短縮型) |
|
|---|---|---|---|---|
| 返済期間 | 35年 | → | 31年11カ月 (-3年1カ月) |
|
| 毎月返済額 | 1年~/8.5万円 11年~/9.5万円 21年~/10.2万円 31年~/10.5万円 |
→ | 1年~/8.5万円 11年~/9.4万円 21年~/9.9万円 31年~/10.0万円 |
|
| 総支払額 | 4014万円 | → | 3804万円 (-210万円) |
|
期間を短縮した結果、借入期間は3年1カ月短縮できます。借入期間は35年なので、それほど短くなっていないと考えるかもしれませんが、金利が上昇している最後の3年1カ月の支払いがなくなるので、金利上昇に対する効果は大きいと言えます。
ただし、毎月支払額は、返済額軽減型に比べると上昇します。31年目以降の毎月支払額は10.0万円で、当初に比べて1.5万円アップしました。こうした負担増に耐えられると考えるなら、「期間短縮型」を選択してもいいでしょう。
(C)変動金利と固定金利のミックスローン
別のリスク軽減策としては、(C)変動金利と固定金利のミックスローンを借りてもいいでしょう。
「繰上返済のような手続きをこまめにしたくない」という人におすすめです。最近は住宅ローン契約は1つでも、ミックスローンを利用できるという金融機関も登場し、使い勝手が良くなっています。
ミックスローンの内訳は以下のとおりです。
・借入額3000万円
・うち、変動金利で1500万円(金利1%から10年ごとに1%上昇)
・うち、35年固定金利で1500万円(金利1.5%)
全額を変動金利で借りたケースと、ミックスローンを比較してみましょう。
|
ミックスローンは金利上昇の緩和効果が高い! (借入金額3000万円、借入期間35年、変動金利は1%から10年ごとに1%アップ) |
|||
| 商品 | 変動金利だけ | → |
ミックスローン (変動金利1500万円+ 35年固定1500万円) |
|---|---|---|---|
| 返済期間 | 35年 | → | 35年 |
| 毎月返済額 | 1年~/8.5万円 11年~/9.5万円 21年~/10.2万円 31年~/10.5万円 |
→ | 1年~/8.8万円 11年~/9.4万円 21年~/9.7万円 31年~/9.8万円 |
| 総支払額 | 4014万円 | → | 3935万円 (-79万円) |
ミックスローンは、35年固定金利で借りた分の金利が1.5%と高いため、当初の毎月支払額は8.8万円と、変動金利だけで借りた場合に比べて0.3万円高くなります。
ただし、金利が上昇する11年目以降は、状況が一変します。借入額の半分は固定金利で、毎月支払額が変動せず、変動金利の分だけが毎月支払額が増加するので、上昇の仕方が緩やかになるのです。
結果として、31年目以降は、毎月支払額が9.8万円となり、変動金利だけの場合にくらべて0.7万円少なくなりました。
一度借りてしまったら、その後のメンテナンスをしなくても金利上昇リスクをある程度抑えられるので、こまめでない人に向いているといえます。
なお、これまで紹介してきた「繰上返済」と「ミックスローン」を併用してもいいでしょう。この組み合わせによる、変動金利上昇のインパクトを和らげる効果はさらに大きくなります。
【関連記事】>>「変動金利」「固定金利」「ミックスプラン」住宅ローンの金利タイプの正しい選び方とは?
全期間固定なら、生活設計が立てやすい
ちなみに、「変動金利で借りて金利上昇におびえるのは嫌だ」と考えるのなら、全期間固定で借りるしかありません。
35年固定金利(金利1.5%)だと、毎月支払額は9.2万円、総支払額は3858万円です(借入期間35年、借入額3000万円)。こまごまと繰上返済をする必要がなく、今回の前提条件以上の金利上昇があっても支払額は変わらないので、生活設計が立てやすくて安心です。
固定金利を選ぶべきか、変動金利を選ぶべきかは、将来の金利予想が難しいだけに正しい答えを求めることはできません。自分がどのくらい毎月支払額の上昇に耐えられるかを考えて、自分に最適な金利を選ぶといいでしょう。
ダイヤモンド不動産研究所の返済額シミュレーションでは金利上昇パターンも簡単に試算できるので、利用してみてください。
- 新規借入
シミュレーション - 借り換え
シミュレーション
(別ページに移動します)
-
「住宅ローン金利の仕組みを徹底解説」の連載
- 第1回 市場金利は「景気」の影響受けない!?
第2回 変動金利を2年以内に引き上げる銀行は4行!?
第3回 営業戦略から見る、変動金利引き上げ時期
第4回 「全期間固定金利」は、バーゲン的な低金利
第5回 「全期間固定金利」が割安と言える理由は?
第6回 「ミックスプラン」も考えてみよう
| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[新規借入] |
| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[借り換え] |
 |
 |
| 【金利動向】おすすめ記事 | 【基礎】から知りたい人の記事 |
| 【今月の金利】 【来月の金利】 【2025年の金利動向】 【変動金利】上昇時期は? 【変動金利】何%上昇する? |
【基礎の8カ条】 【審査】の基礎 【借り換え】の基礎 【フラット35】の基礎 【住宅ローン控除】の基礎 |
新規借入2026年1月最新 主要銀行版
住宅ローン変動金利ランキング
※借入金額3000万円、借入期間35年で試算
- 実質金利(手数料込)
- 0.722%
- 総返済額 3387万円
- 表面金利
- 年0.590%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 79,074円
①保証料など0円サービスが充実
②新規借入の場合は自己資金10%以上で金利優遇あり
③最大3億円まで借入可能


![]()
住宅ローン 全期間引下げ(新規借入)・変動金利
- 実質金利(手数料込)
- 0.762%
- 総返済額 3410万円
- 表面金利
- 年0.630%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 79,611円
①低金利の上、がん50%団信無料
②無料で全疾病保償&12カ月の就業不能保償を付帯
③金利+0.1%で、がん100%団信も付帯OK


- 実質金利(手数料込)
- 0.782%
- 総返済額 3421万円
- 表面金利
- 年0.650%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 79,880円
①店舗相談でも、低金利商品あり
②新規借入なら、注文住宅で必要な「つなぎ融資」に対応!
③3大疾病の50%保障が無料付帯!
④無料で、3大疾病50%保障&就業不能保障&就業不能保障を付帯する


-
住宅ローン利用者口コミ調査の詳細を見る
-
今回作成した「住宅ローン利用者口コミ調査」の調査概要は以下のとおり。
【調査概要】
調査日:2023年12月
調査対象:大手金融機関の住宅ローン利用者(5年以内に住宅ローンを新規借り入れ、借り換えした人)
有効回答数:822人
調査:大手アンケート調査会社に依頼
評価対象:有効回答数47以上を対象とするアンケートの設問は以下の7問。回答は5段階評価とした。なお、評価点数の平均点は小数点第2位以降を四捨五入。
【アンケートの設問】
Q1.金利の満足度は?
Q2.諸費用・手数料等は妥当でしたか?
Q3.団体信用生命保険には満足しましたか?
Q4.手続き・サポートには満足しましたか?
Q5.審査について、満足していますか?
Q6.借り入れ後の対応に満足しましたか?
Q7.他の人にも現在の銀行を勧めたいと思いますか?
【回答の配点】
・各設問は5段階で回答してもらい、Q1なら以下のように配点。平均値を求めた。
満足している(5点)
どちらかといえば満足している(4点)
どちらともいえない(3点)
どちらかといえば不満である(2点)
不満である(1点)
・総合評価については、各項目の平均値を全て合算。読者が重視する「Q1金利の満足度」については点数を3倍、「Q3団信の満足度」の点数を2倍として、点数の合計を50点満点とし、10で割ることで5点満点の数値を求めた。
|
保証料や団信などの諸費用がほとんど無料  |
|
132銀行の住宅ローンを比較 >>返済額シミュレーションで、全銀行の金利を一気に比較・調査
|
- 年収に対して安心して買える物件価格は?
-
- ・年収200万円で妻が妊娠中の家族の上限は1600万円!?
- ・年収250万円の単身者の上限は1800万円!?
- ・年収300万円の4人家族の上限は1800万円!?
- ・年収350万円の2人家族の上限は2100万円!?
- ・年収400万円の単身者の上限は2500万円!?
- ・年収450万円の4人家族の上限は2000万円!?
- ・年収500万円の4人家族の上限は3000万円!?
- ・年収600万円の3人家族の上限は3500万円!?
- ・年収600万円の40代独身の上限は3000万円!?
- ・年収700万円の共働き夫婦の上限は5000万円!?
- ・年収800万円の3人家族の上限は4500万円!?
- ・年収1000万円の30代4人家族の上限は5000万円!?
- ・年収1000万円の40代4人家族の上限は3500万円!?
- ・年収1000万円の50代夫婦の上限は3000万円!?
※サイト内の金利はすべて年率で表示







 関連記事
関連記事

プロの評判・口コミ
淡河範明さん
SBI新生銀行の住宅ローンは、10年固定、15年固定、20年固定といった金利が低い点が特徴です。
商品も特徴的で、介護状態を保障する団信や、長く借りていると金利が下がっていく「ステップダウン金利」があるのも主要銀行ではここだけです。
審査はオーソドックスに行なっている感じです。住宅ローン処理センターで集中審査しているので、窓口のかたの力量があまり問われず、公平に審査されるという印象です。
なお、相談から審査、契約の手続きまでネットで完結できるようになりました。不安な方には、ビデオ通話で自宅から気軽に相談ができるので、コロナ禍の現状では最適な方法が用意されているようです。