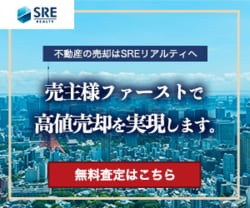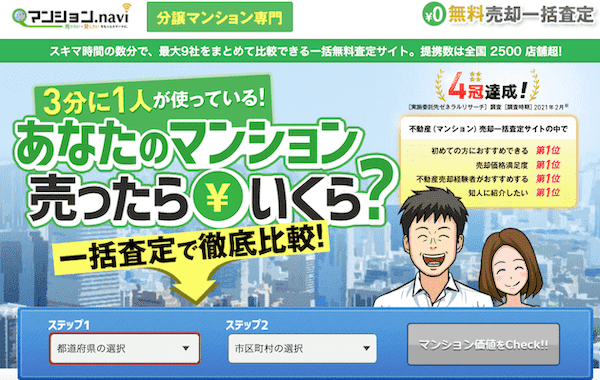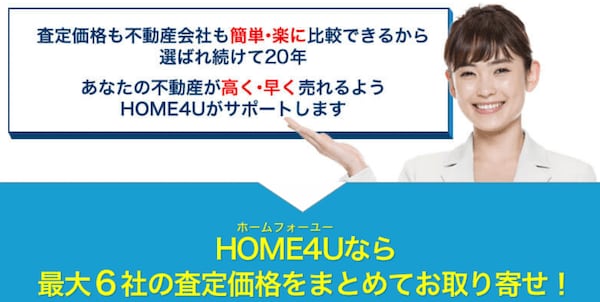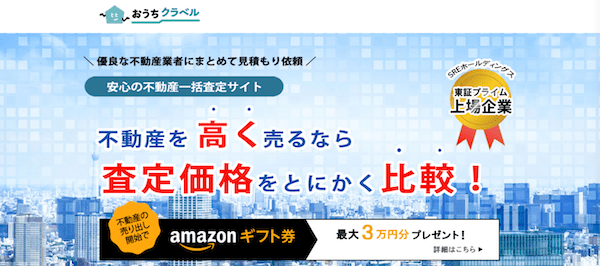「遺留分」制度とは、一定範囲の相続人に対して、相続財産の一定部分を留保させること。しかし、遺言によって自分の遺留分が侵害されて、かつ争いとなったとき、従来の取り戻しの請求方法では手続き的にもコスト的にもハードルが高かった。それが"平成31年度の相続法(民法相続編)改正"の遺留分制度の見直しによって改善される。何がどう変わるのか、詳しく見ていこう。(取材協力・監修:法律事務所アルシエン 武内優宏弁護士)
(1) 「配偶者居住権」のメリット
(2) 「特別受益の持ち戻し免除の推定」とは
(3) 「自筆証書遺言」の要件緩和と、新たな保管方法
(4) 「遺産分割前の預貯金の引き出し」の柔軟化
(5) 「相続登記における対抗要件」の変更
(6) 「遺留分」制度の見直しの影響
一定の遺族の生活保障などのために認められた「遺留分」
相続においては、亡くなった人(被相続人)は遺言によって自分の死後、自分の財産をどのように処分するか自由に決められるのが原則である。法律で定められた相続人だけでなく、赤の他人に自分の財産を渡すことも可能だ。
例えば、被相続人が糟糠の妻を見捨て、「遺産は全て愛人に相続させる」と遺言することも理屈の上ではできる。
その一方、法律で定められた相続人には、亡くなった人(被相続人)の財産を相続できるだろうという期待があるし、とりわけ近しい親族については、被相続人の生前、その財産を築く上で一定の貢献があっただろうし、また被相続人が亡くなった後の生活を保障する必要性もある。
そこで民法では、一定範囲の相続人に対して、相続財産の一定部分を留保させることにしている。
これが「遺留分」とよばれる制度だ。
「遺留分」制度で重要なのは、遺留分が認められる相続人であっても、自動的に遺留分がもらえるわけではないということ。
亡くなった人(被相続人)が、遺留分を侵害するような内容の遺言をつくっている場合もあるからだ。
亡くなった人(被相続人)の遺言によって、自分の遺留分を侵害されたことを知った場合は、まず、相続人がそれぞれ個別に、侵害された分の取り戻しの請求を行わなければならない。
この請求を、従来は「遺留分減殺請求」、今回の改正により「遺留分侵害額請求」と呼ぶ。いずれの請求も、必ずしも裁判で行う必要はなく、侵害した相手方(相続人や受贈者)に対する一方的な意思表示で足りる。
従来の「遺留分」の請求には難点があった

ここからは今回の改正の経緯を見ていこう。
従来の「遺留分減殺請求」は"物権的効果"を生じるとされた。物権的効果の代表的なケースは所有権が生じるということであり、土地建物などの不動産であれば共有状態になるということだ。
しかし、これにはいろいろ不都合が指摘されていた。
そもそも、遺留分減殺請求により物権的効果が生じるとしても、遺留分を巡って当事者同士が争っているわけで、簡単に話し合いですんなり解決することはまずない。
相手から裁判を起こされたり、財産の保全など別の手続きが必要だったりするため、遺留分について決着するには2~3年かかることもざらだ。
また、遺留分について決着しても、特に自宅の土地建物の共有持ち分を持っていても財産上のメリットはほとんどない。共有持ち分だけを市場で売却するのもまず不可能だ。そこでさらに、共有物である不動産の分割請求訴訟を起こさなければならない。
不動産は時価が分かりにくく、その分割ともなれば不動産鑑定が必要になることが多い。これでまた2~3年はかかり、不動産鑑定の費用も数十万円から100万円以上かかることも珍しくない。
今回の改正で金銭の支払い請求が原則に
このように従来の遺留分減殺請求は手続き的にもコスト的にも面倒で、ハードルが高かった。
そこで今回の民法改正では、遺留分侵害に対する請求においては、金銭の支払い請求を原則とすることになった。「遺留分侵害額請求」を行うと、金銭債権が発生するということだ。
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む、以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害に相当する金銭の支払いを請求することができる。
※2項省略
これにより、遺留分の争いの解決にかかる裁判等の期間はある程度、短縮されることになるだろう。
ただし、不動産の価額をどのように評価するかという問題はやはり残っており、不動産鑑定が必要となることも変わらないと思われる。
また、今回の改正では、遺留分侵害額の計算方法についても、次のように明確化された。
遺留分侵害額 = (遺留分)-(遺留分権利者が受けた特別受益)-(遺留分権利者が取得すべき具体的相続分)+(遺留分権利者が承継する相続債務の額)
「遺留分算定の財産の価格」の計算において、基準は相続開始時である。不動産の価格も相続開始時で固定される。
従来の遺留分減殺請求では、不動産はいったん共有となり、その後、先ほど述べたように共有物の分割請求訴訟を行う必要があった。その場合、不動産の価格は分割時点が基準となる。
相続開始時と、数年にわたる裁判の後で、不動産の価格がどのように変化しているかは立地などにより一概にはいえないが、遺留分権利者にとって、地価が下落傾向にあるような場合は、相続開始時で固定されたほうが有利である。
また、「遺留分算定の財産の価格」の計算において、相続人に対する生前贈与は原則として10年以内、第三者に対する生前贈与については1年以内に限定して、含めることになった。
こちらは、遺言で法定相続分を超える遺産を引き継ぐ受遺者や受贈者に、不測の損害を与えないようにするものといえる。
なお、最後にもう一つだけ、遺留分侵害に対する請求での注意点を挙げておきたい。
従来の遺留分減殺請求権も、改正後の遺留分侵害額請求権も、遺留分を侵害された相続人が、相続があったことに加え、自分の遺留分を侵害する遺言による贈与や遺贈があったことを知ったときから1年で時効によって消滅する。相続開始のときから10年経った場合も、同じく時効により消滅するので注意が必要だ。
いずれにしろ、亡くなった人(被相続人)の立場からすると、遺言で特定の相続人などに法定相続分を超える遺産を渡そうとするのであれば、減殺請求(侵害額請求)への対応を含めて遺言しておくことが重要であろう。
【関連記事はこちら】>>自筆証書遺言と公正証書遺言、おすすめはどっち?
法改正による要件緩和や保管制度のメリットを検証!
(補足)遺留分が認められる相続人とは
相続人になるのは妻(配偶者)、子、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹のいずれかだ。
このうち、配偶者は必ず相続人になる。
配偶者がいて、そのほかに子(子がすでに亡くなっていればその子など)がいれば配偶者と子(同)、子がいなくて直系尊属がいれば配偶者と直系尊属、直系尊属もいなければ配偶者と兄弟姉妹が、それぞれ相続人になる。
配偶者がいない場合、子がいれば子、子がいなくて直系尊属がいれば直系尊属、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が、相続人になる。
これらの組み合わせのうち、遺留分が認められる相続人は、配偶者、子、直系尊属に限られる。兄弟姉妹は含まれない。つまり、相続人が兄弟姉妹だけの場合に限り、被相続人は遺言で遺産を自由に処分できる。
認められる遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1であり、配偶者と他の相続人との割合は下の図表の通りだ。
| ■相続人の組み合わせと遺留分 | ||
| 相続人の組み合わせ | 遺留分 | 各人の遺留分 |
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者 1/2 |
| 子のみ | 1/2 | 子 1/2 |
| 配偶者と子 | 1/2 | 配偶者 1/4、子 1/4 |
| 配偶者と直系尊属 | 1/2 | 配偶者 2/6、子 1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者 1/2、兄弟姉妹 なし |
| 直系尊属のみ | 1/3 | 直系尊属 1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | なし | なし |
| ※子や直系尊属が複数いる場合は、「各人の遺留分」をその人数で均等に分ける | ||
(1) 「配偶者居住権」のメリット
(2) 「特別受益の持ち戻し免除の推定」とは
(3) 「自筆証書遺言」の要件緩和と、新たな保管方法
(4) 「遺産分割前の預貯金の引き出し」の柔軟化
(5) 「相続登記における対抗要件」の変更
(6) 「遺留分」制度の見直しの影響
・相続で必要な書類、スケジュールは?
・相続の相談は税理士、弁護士等のだれがいい?
・相続税の計算方法と、節税のポイントは?
・相続税のほかにかかる「税金」と「諸費用」
・タワマンや社団法人を利用した相続税対策
AI査定×エージェント制「SREリアルティ」の不動産査定
SREリアルティは、東証プライム上場のソニーグループ関連会社が運営する不動産仲介会社で、売却専門エージェントが担当する「片手仲介」が特徴です。売主に寄り添うサポート力に強みがあり、顧客満足度93%と高い評価を得ています。ソニーグループと共同開発したAI技術を査定にも活用。高値売却を目指したい方におすすめです。(※対応エリア:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都府)
※不動産一括査定サイトでは、売却したい不動産の情報などを入力すれば、無料で複数社に査定依頼ができます。査定額を比較できるので売却相場が分かり、きちんと売却してくれる不動産会社を見つけやすくなる便利なサービスです。
| ◆SUUMO(スーモ)売却査定 | |
|
無料査定はこちら >> |
|
| 特徴 | ・圧倒的な知名度を誇るSUUMOによる一括査定サービス ・主要大手不動産会社から地元に強い不動産会社まで2000社以上が登録 |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地 |
| 紹介会社数 | 10社(主要一括査定サイトで最多)※査定可能会社数は物件所在地によって異なります |
| 運営会社 | 株式会社リクルート(東証プライム) |
|
|
|
| ◆すまいValue | |
|
|
|
| 特徴 | ・大手不動産会社6社が運営する一括査定サイト |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション、一棟アパート、一棟ビル |
| 対応エリア | 北海道、宮城、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、愛知、岐阜、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、岡山、広島、福岡、佐賀 |
| 運営会社 | 大手不動産会社6社(東急不動産、住友不動産ステップ、三井のリハウス、三菱地所の住まいリレー、野村の仲介+、小田急不動産) |
|
|
|
| ◆マンションナビ | |
|
無料査定はこちら >> |
|
| 特徴 |
・マンションの売却に特化 |
|---|---|
| 対応物件 | マンション |
| 紹介会社数 | 最大9社(売却・買取6社、賃貸3社) |
| 運営会社 | マンションリサーチ |
|
|
|
| ◆HOME4U(ホームフォーユー) | |
|
無料査定はこちら >> |
|
| 特徴 | ・悪質な不動産会社はパトロールにより排除している ・20年以上の運営歴があり信頼性が高い ・2500社の登録会社から最大6社の査定が無料で受け取れる |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、ビル、アパート、店舗・事務所 |
| 紹介会社数 | 最大6社 |
| 運営会社 | NTTデータ・ウィズ(東証プライム子会社) |
|
|
|
| ◆リビンマッチ | |
| 特徴 |
・マンション、戸建、土地のほか、工場、倉庫、農地の査定にも対応可能 ・1700社の不動産会社と提携 |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫 |
| 紹介会社数 | 最大6社(売却6社、賃貸、買取) |
| 運営会社 | リビン・テクノロジーズ(東証グロース上場企業) |
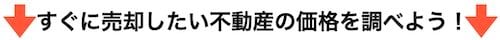
| ◆いえカツLIFE | |
|
無料査定はこちら >> |
|
| 特徴 |
・対応可能な不動産の種類がトップクラス |
|---|---|
| 対応物件 | 分譲マンション、一戸建て、土地、一棟アパート・マンション・ビル、投資マンション、区分所有ビル(1室)、店舗、工場、倉庫、農地、再建築不可物件、借地権、底地権 |
| 紹介会社数 | 最大6社(売買2社、買取2社、リースバック2社) |
| 運営会社 | サムライ・アドウェイズ(上場子会社) |
|
|
|
| ◆おうちクラベル | |
|
無料査定はこちら >> |
|
| 特徴 |
・AI査定で、査定依頼後すぐに結果が分かる |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション、一棟アパート |
| 紹介会社数 | 最大9社 |
| 運営会社 | SREホールディングス株式会社(東証プライム上場企業) |
|
|
|
| ◆イエウール | |
|
無料査定はこちら >> |
|
| 特徴 |
・掲載企業一覧を掲載、各社のアピールポイントも閲覧可能 |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地 |
| 紹介会社数 | 最大6社 |
| 運営会社 | Speee |
|
|
|
| ◆LIFULL HOME'S(ライフルホームズ) | |
|
無料査定はこちら >> |
|
| 特徴 |
・日本最大級の不動産ポータルサイト「LIFULL HOME'S」が運営 |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、倉庫・工場、投資用物件 |
| 紹介会社数 | 最大6社 |
| 運営会社 | LIFULL(東証プライム) |
|
|
|
不動産一括査定サイト10社を比較
| サイトロゴ |  |
 |
 |
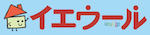 |
 |
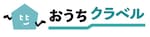 |
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス名 | suumo売却査定 | すまいValue | HOME4U | イエウール | ライフルホームズ | おうちクラベル | イエイ | マンションナビ | リビンマッチ | いえカツLIFE |
| ポイント | 知名度の高いスーモで、大手から地元の会社まで様々な不動産会社に査定を依頼できる。当社調査で満足度No.1 | 大手不動産仲介6社の共同運営で、査定が可能。都市圏の物件に強い。大手の査定結果を比較するのに便利。 | NTTデータの子会社が運営。20年以上の運営歴で安心感がある。大手のほか、店舗や事務所の査定にも対応。 | 都市圏だけでなく、地方の不動産会社も提携多数。対応する物件タイプが豊富で、農地の査定にも対応している。 | 匿名でも査定が可能。提携社数が多く、投資用物件の査定にも対応。東証プライム上場。当社調査で満足度No.2 | 東証プライム上場企業が運営。AI査定ですぐに結果が分かる。売り出し開始でAmazonギフト券最大3万円プレゼント。 | 仲介営業のお断り代行サービスが特徴。査定から成約まで完了でAmazonギフト券最大10万円贈呈。東証プライム上場企業が運営。 | マンションに特化。売却・賃貸、両方の査定が分かる。マンション売買の分析データに詳しい。マンション査定なら選択肢に入れたい。 | 都市部だけでなく、地方の不動産会社とのネットワークが充実。幅広いエリアで査定対応している。20年の運営実績あり。 | 急ぎの売却や訳あり物件の査定に強み。3つの売却方法(仲介、買取、リースバック)を選べる。 |
| ユーザー満足度※ | 3.8 ★★★★★ |
3.4 ★★★★★ |
3.4 ★★★★★ |
3.3 ★★★★★ |
3.6 ★★★★★ |
3.1 ★★★★★ |
3.6 ★★★★★ |
2.8 ★★★★★ |
3.2 ★★★★★ |
ー |
| 提携社数 | 2000以上 | 大手6社 (住友不動産ステップ、東急リバブル、三井のリハウス、野村の仲介など) |
2500以上 | 2600以上 | 4900以上 |
1500 |
1700以上 | 2500 | 1700以上 | 500 |
| 最大紹介社数 | 10社 ※物件所在地によって異なる |
6社 | 6社 | 9社 | 6社 |
9社 |
7社 | 9社 (売却6社、賃貸3社) |
6社 | 6社 (仲介2社、買取2社、リースバック2社) |
| 主な対応物件 | マンション、戸建て、土地 | マンション、戸建て、土地 | マンション、戸建て、土地、ビル一室、店舗・事務所・倉庫、マンション一棟、アパート一棟、ビル一棟 | マンション、戸建て、土地、ビル一室、店舗・事務所・倉庫、マンション一棟、アパート一棟、ビル一棟、区分マンション(収益)、区分ビル(ビル一室)、農地 | マンション、戸建て、土地、マンション一棟、アパート一棟、ビル一棟、倉庫・工場 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション・アパート、店舗、事務所 | マンション、戸建て、土地 | マンション | マンション、戸建て、土地、一棟アパート・一棟マンション、投資マンション(1R・1K)、一棟ビル/区分所有ビル(ビル1室)、店舗・工場・倉庫、農地、その他 | マンション、戸建て、土地、再建築不可物件、借地権、底地権、その他(共有持分も査定・売却対象)など |
| 対応エリア | 全国 | 全国(一部を除く) | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 東京・神奈川・千葉・埼玉 |
| 解説記事 | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら |
| 公式サイト | 詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
詳細を見る (無料査定も可能) |
※ユーザー満足度は、ダイヤモンド不動産研究所が独自にアンケート調査した結果をもとに算定。詳しい記事はこちら
|
【不動産仲介会社の評判を徹底調査!】 |