住宅ローンは、「80歳までに完済する」などの年齢に関する審査基準を設けていることが多い。そこで主要15銀行の住宅ローンの「完済時の年齢」「借入時の年齢」を比較してみた。なお、定年後も返済が続くようだと、返済が苦しくなる可能性もあるので、借入期間や借入額の設定には注意点したいところだ。
完済時の年齢は、「85歳未満」という銀行も
従来、住宅ローンの審査基準で、完済時の年齢(上限年齢)を80歳にしていたのは、半官半民の住宅ローンである「フラット35」くらいだった。一方で、民間の銀行・金融機関の完済時の年齢もそれに合わせて、徐々に融資条件が甘くなっている。最近では多くの銀行・金融機関が年齢を80歳まで延ばしている。
下表が調査した結果だ。
| 銀行名 | 完済時の年齢 | 借入時の年齢 |
|---|---|---|
| 80歳未満 | 71歳未満 | |
| 80歳の誕生日まで | 65歳未満 | |
| 80歳未満 | 65歳以下 | |
| 80歳未満 | 65歳以下 | |
|
85歳未満 (ワイド団信の場合は81歳未満) |
65歳未満 | |
| 80歳未満 | 65歳6カ月未満 | |
| 80歳未満 | 65歳未満 | |
| ー | ー | |
| 銀行名 | 完済時の年齢 | 借入時の年齢 |
| 81歳未満 | 満18歳以上71歳未満 | |
| 80歳の誕生日まで | 満18歳以上70歳の誕生日まで | |
| 80歳の誕生日まで | 18歳以上70歳の誕生日まで | |
| 80歳未満 | 70歳未満 | |
| 81歳未満 | 66歳未満 | |
| 76歳未満 | 66歳未満 | |
| 80歳未満 | 70歳未満 | |
| ※2023年12月調べ | ||
銀行・金融機関の大半が、完済時の年齢を「80歳未満」「81歳未満」としていた。つまり、45歳までは、借入期間35年の住宅ローンを借りられる銀行が多い。
フラット35の完済時の年齢は「80歳未満」なので、今や民間銀行も同条件か、民間銀行の方が年齢が高い。また、フラット35は返済期間が15年以上の全期間固定ローンであるため金利は高めだが、民間銀行であればさまざまな金利タイプが選べて金利も安いので、借り手にとっては選択肢が広がったことになる。
なお、完済時の年齢が最も高かったのは、ソニー銀行で「85歳未満(ワイド団信の場合は81歳未満)」だった。
住宅ローンは、70歳でも借りられる!
住宅ローンの年齢に関する条件は、ほかにも緩和されている。「借入時の年齢」は、かつては「65歳未満」が主流だったが、最近は「70歳未満」「70歳の誕生日まで」に引き上げた銀行も多い。借入時の年齢が最も高い「71歳未満」に設定しているのは、みずほ銀行とイオン銀行だ。
融資可能額についても、頭金を10%以上用意するのが主流だったが、最近は物件価格と同額まで借りられる「フルローン」(100%ローンとも言う)を認める銀行が増えている。借り換え時にかかる手数料なども融資する「オーバーローン」もネット銀行では一般的だ。審査の際は返済負担率や年収をチェックするとはいえ、年々、借りやすくなっているのは間違いない。
年齢別で注意すべきポイントは?
以上のように、銀行の年齢に関する条件は緩くなっており、年齢上の制約はあまりなくなっている。とはいえ、住宅ローンを検討するときには、きちんと返済できるのか、ライフプランを考えておくことも大切だ。
年齢ごとの借入金額や借入期間などを住宅金融支援機構の調査から見てみよう。調査によれば、30代が最も住宅ローンを利用しており、40代、20代が続く。
- 20歳代:12.2%
30歳代:56.4%
40歳代:25.9%
50歳代:5.5%
家族構成では、「夫婦と子」が最も多い結果となっており、子どもが生まれたり、大きくなったタイミングで住宅購入のために住宅ローンを組んだと推測できる。結婚や子どもの誕生が、住宅購入の大きな動機になるのは間違いなさそうだ。
- 夫婦のみ:24.6%
夫婦と子:59.1%
夫婦と子と親:4.8%
本人と親:2.0%
一人世帯(単身):5.2%
その他:4.3%
※参考:住宅金融支援機構「住宅ローン利用者の実態調査(2021年4月調査)」
サラリーマンや公務員であれば、60歳または65歳で定年を迎える。また、子どもがいれば思った以上の教育費がかかる。老後資金の確保も考えたい。こうした年齢ごとに気をつけるべきポイントがあるので、紹介していこう。
<20代>金利上昇に備えた全期間固定金利がおすすめ
住宅ローンは借入時の年齢が若いと、借入期間を限度いっぱいの35年にしても、完済時はまだ現役で働いている計算になるため問題はない。
一方で20代は就職してから期間が短いために年収は決して多くないので、借入限度額まで借り入れようとする人が多い。そのため少しでも返済額が増加してしまうと住宅ローンの返済が滞ってしまう可能性があるので、変動金利はできれば避けたいところだ。
そこで検討したいのが、全期間固定金利の「フラット35」。住宅金融支援機構と各金融機関とが提携して提供している商品で、借入時の金利がずっと変わらないため、返済も一定で安心感がある。また、10年固定金利も銀行間の競争が激しく、金利が低めなのでおすすめだ。
<30代>教育費など支出が増える前に
住宅金融支援機構の調査を見ると、30代が住宅ローンを一番多く借りている。おそらく、結婚して子どもが生まれるのをきっかけにマイホームを考える人が多いからだろう。子育て世帯の場合、年々教育費が増加していることに注意して、余裕を持った毎月返済額になるように借り入れよう。
一方で、30代で住宅ローンを組む場合、借入期間を最長35年にしても完済時は65歳〜74歳だ。できれば、60歳または65歳の定年時には住宅ローンを完済できることを目指して、少しずつ繰り上げ返済をして、完済時の年齢を引き下げていきたい。比較的、借入期間が長いので、生活費をやりくりして、余裕があるときに繰り上げ返済をすれば安心だろう。
<40代>借入金額と借入期間のバランスを慎重に
会社の中でも責任あるポジションで、収入も増えている年齢だ。一方、子どもがいる場合は、習い事などの教育費の負担も増えるため、支出も大きくなると考えられる。
40歳で借入期間35年で住宅ローンを組むと完済時は75歳になり、定年後にも一定の収入がないと返済が厳しくなるので、借入期間の設定を慎重に考えたい。
なお「退職金で住宅ローンを完済する予定だ」という人が多いが、住宅ローンの完済で退職金が全てなくなってしまうと、老後資金の確保ができなくなるリスクがある。
40代に入って住宅ローンを組む場合は、借入額と借入期間のバランスを考えておこう。
<50代>綿密な住宅ローンの返済計画が重要
定年が見えてくる年齢で、子どもがいる場合は大学進学などの費用の負担が大きい。親の介護の心配もしなければならなくなるケースも多い。
住宅ローンを組む場合は、借入額や借入期間を慎重に検討し、綿密な返済計画を考えておきたい。また、自身の健康面でも不具合が出てくる年代でもあり、病気などで長期入院や手術するリスクも高まってくる。
あらゆるリスクを想定しながら、頭金を多めに入れるなど、ゆとりをもって返済できるように住宅ローンを組むのが大切だ。
65歳までに住宅ローン完済するメリットは?
住宅展示場や新築マンションに行くと、営業マンはどんな年齢の人に対しても35年ローンを提案してくることが多い。返済期間が長ければその分、住宅ローンを多く借りられるため、現在のように不動産価格が高騰していても、不動産を売りやすいからだ。
実際、営業マンに勧められて返済期間を35年として計画を立てる人が多い。しかし借入期間が長いと、デメリットがある。そこで、「70歳完済」「65歳完済」の2ケースについて返済額をシミュレーションして、総支払額などを比較してみよう。
| 年齢 | 毎月支払額 | ||
|---|---|---|---|
| 70歳完済(返済期間35年) | 65歳完済(返済期間30年) | ||
| 36歳(1年目) |
9.2万円 (残高 2934万円) |
→ |
10.4万円 (残高 2920万円) |
| … | … | … | |
| 60歳(25年目) |
9.2万円 (残高 1023万円) |
→ |
10.4万円 (残高 598万円) |
| 65歳(30年目) |
9.2万円 (残高 531万円) |
→ |
10.4万円 (残高 0円) |
| 70歳(35年目) |
9.2万円 (残高 0円) |
→ | ― |
| 総支払額 | 3858万円 | → | 3727万円 |
| ポイント | 60~70歳の間、毎月9.2万円を支払い続けられるのかがポイント | 毎月返済額は70歳完済に比べて1.2万円高いが、老後の不安は減少 | |
| ※35歳、借入金額3000万円、金利1.5%(全期間固定金利)。毎月返済額は1000円未満を、残高は1万円未満を四捨五入 | |||
70歳完済(返済期間35年)の場合、毎月の住宅ローン支払額は9.2万円だ。多くのサラリーマンや公務員は60〜65歳で退職して収入が減少することが多いので、定年後は年金があったとしても、住宅ローンの支払いに困るかもしれない(公的年金は1961年4月2日以降に生まれた男性は65歳から受給可能。女性は1966年4月2日生まれ以降が65歳から受給可能)。
では、退職金で住宅ローン残高を一括払いすればいいのだろうか。60歳時点での住宅ローン残高を見てみると1023万円と多額の住宅ローンが残っている。老後に備えた貯金もしたい時期だけに、住宅ローンの残高を支払えるとしても、かなり手痛い出費になる。
そこで考えられる対策が、「65歳完済(返済期間30年)」だ。毎月支払額は10.4万円と、1.2万円アップするが、総支払額は131万円(=3858万円-3727万円)も抑えることができる。60歳時点での住宅ローン残高は598万円とそれなりにあるが、70歳完済に比べればかなりましだ。借入期間を短くすると、総支払額が少なくてすむというメリットがあるのだ。
ファイナンシャルプランナーの深田晶恵さんは、次のように指摘する。
「おすすめは、どんなに遅くとも65歳までに完済することです。65歳から『ローンの返済が始まるときの年齢』を引いたものが“最長の返済期間”と考えましょう」
つまり、年齢ごとの借入期間の目安は以下のようになる。
- ・35歳なら、借入期間30年
・40歳なら、借入期間25年
・45歳なら、借入期間20年
・50歳なら、借入期間15年
老後が不安なら、65歳までに完済が得策
一方、「住宅ローンの支払いは65歳までにとどめたいが、それだと返済が大変」という人は、物件価格を引き下げるしかない。
65歳までに返済(借入期間30年)の場合、借入金額ごとの毎月返済額は、返済額シミュレーションを使えば判明する。ダイヤモンド不動産研究所の返済額シミュレーションだと、以下のような結果となった。
・借入金額2800万円:毎月返済額8.9万円〜
・借入金額2600万円:毎月返済額8.3万円〜
※2022年1月調べ。全期間固定で、132銀行のローンを対象に調査
当初の希望物件は購入できないかもしれないが、駅から遠い物件を探すなど、条件を多少引き下げることで対応可能だろう。
なお、実際に借りる場合は、あえて70歳完済にして、余裕があるときに繰り上げ返済することで、65歳完済と同じ効果を得てもいい。急な出費にそなえて、預金を一定額確保しておこう。
【関連記事はこちら】>> 年収不足で、住宅ローンを借り換えできない?! 収入合算、返済期間延長の裏技を使おう!
オプション団信に加入できる年齢に制限がある
なお、住宅ローンを組む場合、死亡や高度障害になるリスクを考えて団体信用生命保険(団信)に加入する人も多い。住宅ローンとセットになっている生命保険で、万一の場合は住宅ローン残高がゼロになるというものだが、加入時の年齢に条件がついている。
一般的な団信については、基本的に加入が義務付けられており、借入時の年齢と一緒だ(65歳以下〜70歳以下のケースが大半)。
問題なのは、保障を充実できるオプション団信(「がん保障団信」「3大疾病保障団信」「7大・8大・11大疾病保障団信」など)だ。加入時の年齢が「50歳未満」に設定されていることが多い。こうした疾病保障にどうしても加入したい場合は、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行であれば、加入年齢が「56歳未満」と高めの団信も用意しているので、検討してみよう。
【関連記事はこちら】>>「団体信用生命保険」徹底比較!住宅ローンでおすすめの団信は?
| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[新規借入] |
| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[借り換え] |
 |
 |
| 【金利動向】おすすめ記事 | 【基礎】から知りたい人の記事 |
| 【今月の金利】 【来月の金利】 【2025年の金利動向】 【変動金利】上昇時期は? 【変動金利】何%上昇する? |
【基礎の8カ条】 【審査】の基礎 【借り換え】の基礎 【フラット35】の基礎 【住宅ローン控除】の基礎 |
新規借入2026年2月最新 主要銀行版
住宅ローン変動金利ランキング
※借入金額3000万円、借入期間35年で試算
![]()
住宅ローン 全期間引下げ(新規借入)・変動金利
- 実質金利(手数料込)
- 0.762%
- 総返済額 3410万円
- 表面金利
- 年0.630%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 79,611円
低金利の上、がん50%団信無料


- 実質金利(手数料込)
- 0.772%
- 総返済額 3415万円
- 表面金利
- 年0.640%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 79,745円
①保証料など0円サービスが充実
②新規借入の場合は自己資金10%以上で金利優遇あり
③最大3億円まで借入可能


- 実質金利(手数料込)
- 0.782%
- 総返済額 3421万円
- 表面金利
- 年0.650%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 79,880円
①ネット銀行の低金利を店頭相談で申し込める!
②51歳以下なら3大疾病保障特約(50%)が無料で基本付帯
③新規借入なら、注文住宅で必要な「つなぎ融資」に対応


-
住宅ローン利用者口コミ調査の詳細を見る
-
今回作成した「住宅ローン利用者口コミ調査」の調査概要は以下のとおり。
【調査概要】
調査日:2023年12月
調査対象:大手金融機関の住宅ローン利用者(5年以内に住宅ローンを新規借り入れ、借り換えした人)
有効回答数:822人
調査:大手アンケート調査会社に依頼
評価対象:有効回答数47以上を対象とするアンケートの設問は以下の7問。回答は5段階評価とした。なお、評価点数の平均点は小数点第2位以降を四捨五入。
【アンケートの設問】
Q1.金利の満足度は?
Q2.諸費用・手数料等は妥当でしたか?
Q3.団体信用生命保険には満足しましたか?
Q4.手続き・サポートには満足しましたか?
Q5.審査について、満足していますか?
Q6.借り入れ後の対応に満足しましたか?
Q7.他の人にも現在の銀行を勧めたいと思いますか?
【回答の配点】
・各設問は5段階で回答してもらい、Q1なら以下のように配点。平均値を求めた。
満足している(5点)
どちらかといえば満足している(4点)
どちらともいえない(3点)
どちらかといえば不満である(2点)
不満である(1点)
・総合評価については、各項目の平均値を全て合算。読者が重視する「Q1金利の満足度」については点数を3倍、「Q3団信の満足度」の点数を2倍として、点数の合計を50点満点とし、10で割ることで5点満点の数値を求めた。
|
保証料や団信などの諸費用がほとんど無料  |
|
132銀行の住宅ローンを比較 >>返済額シミュレーションで、全銀行の金利を一気に比較・調査
|
- 年収に対して安心して買える物件価格は?
-
- ・年収200万円で妻が妊娠中の家族の上限は1600万円!?
- ・年収250万円の単身者の上限は1800万円!?
- ・年収300万円の4人家族の上限は1800万円!?
- ・年収350万円の2人家族の上限は2100万円!?
- ・年収400万円の単身者の上限は2500万円!?
- ・年収450万円の4人家族の上限は2000万円!?
- ・年収500万円の4人家族の上限は3000万円!?
- ・年収600万円の3人家族の上限は3500万円!?
- ・年収600万円の40代独身の上限は3000万円!?
- ・年収700万円の共働き夫婦の上限は5000万円!?
- ・年収800万円の3人家族の上限は4500万円!?
- ・年収1000万円の30代4人家族の上限は5000万円!?
- ・年収1000万円の40代4人家族の上限は3500万円!?
- ・年収1000万円の50代夫婦の上限は3000万円!?
※サイト内の金利はすべて年率で表示






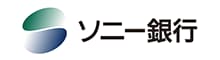




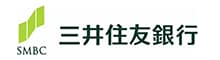

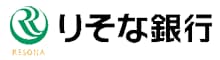







 関連記事
関連記事


プロの評判・口コミ
淡河範明さん
PayPay銀行の住宅ローンは、ネット銀行ならではの低金利が特徴です。がん50%団信も付帯するようになり、auじぶん銀行などと人気を分けています。
ネット銀行ならではの、お申込みから契約までネットでお手続きを完結できる点も魅力的です。
ただし、審査は厳しめです。
条件のいい借り手に絞ることで低金利を実現しているものと思われます。当初の計画では、徐々に融資対象を拡大していくとしていましたが、今後どうするのか注目しています。