2025年9月の金融政策決定会合で政策金利は据え置きでした。本記事では、会合後の植田日銀総裁の会見を深掘りし、政策金利の出口と今後の到達金利のシナリオを独自に予想しました。これを踏まえて、今後の住宅ローンの金利動向をフラット35、民間銀行の金利タイプごとに解説します。(住宅ローン・不動産ブロガー 千日太郎)
2025年9月の日銀会合、政策金利は据え置き
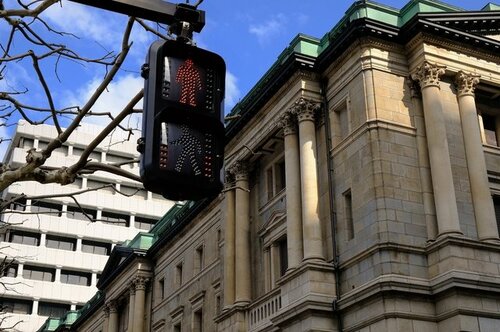
こんにちは、公認会計士の千日太郎です。
2025年9月に開かれた日銀の金融政策決定会合では、市場の予想どおり政策金利は、0.5%程度で据え置きでした。米国の関税政策による経済への不確実性を懸念したものですが、私は単純にハト派※とは見ていません。
※景気刺激策に積極的で金融緩和策を好む人々。その反対をタカ派という。
同時に、上場投資信託(ETF)や不動産投資信託(J-REIT)の売却を決定しています。これは、黒田前日銀総裁時代の異次元緩和政策からの正常化に向けて舵を切ったものであり、いよいよ出口に向けた局面に入ったといえるでしょう。
ただ、全量を売却するには100年以上かかるとの試算です。それでも、市場に影響しない規模感で粛々と処理を進める姿勢は、正常化を前に進める強い意思の表れと見ています。
政情不安がある中で利上げを避けつつも、市場に対して利上げ姿勢を継続するというメッセージを残したということになります。(出典:日本銀行「当面の金融政策運営について 2025年9月19日」)
会合後の国内債券市場での新発10年国債利回りは、前日終値の1.600%よりも0.041ポイント高い1.641%で取引を終えています。
今回は、「金利据え置きでも利上げ継続」という市場とのコミュニケーションが反映されたものと見ています。
今後の利上げ時期による到達金利のシナリオ
ここからは、住宅ローンを検討している方に向けて、日銀の今後の利上げタイミングと到達金利(ターミナルレート)※と利上げ後の景気動向を予測します。
※金融引き締めを目的とした利上げサイクルの最終的な着地点となる政策金利水準を指す。
物価の上昇が本格化する前に利上げを始めるオンタイムであれば、回数を少なく抑えられ、金利も低く収まる可能性があります。
逆に利上げが遅れるビハインド・ザ・カーブの場合は、追加引き上げが必要になり、金利は上振れしやすくなります。
また、利上げが早すぎると景気が冷え込み、到達金利に達する前に打ち止めとなるケースも考えられます。
10月に利上げがある場合
10月に利上げが行われた場合、米国の関税政策などの悪影響が出なければ、オンタイムで対応できる可能性と、ビハインド・ザ・カーブである可能性の両方があります。この場合、到達金利は条件によって異なります。
物価が2%台前半で落ち着けば、政策金利は1.0%前後への引き上げにとどまる可能性が高いでしょう。逆に、インフレ圧力が続き、需要も強い状態が続けば、1.5%〜2.0%程度まで上限金利を引き上げざるを得ない展開も想定されます。依然としてやや広いレンジでの可能性が維持されると見ています。
そして、同じ10月利上げでも、米欧の景気悪化に巻き込まれて景気が早期に減速し関税の影響が強く出れば、その時点で利上げは打ち止めとなってしまいます。この場合は0.75%が上限になるでしょう。変動金利で実行予定の人には有利になります。
ただ、金融政策の正常化を目指している日銀としては避けたいと思っているシナリオの一つです。
12月~来年1月に利上げがある場合
一方で、12月や来年1月まで利上げが見送られた場合ですが、これもオンタイム寄りでしょう。
日銀が経済や物価情勢の展望で成長鈍化を予想している2026年度には少なくとも1回。回復が予想される2027年度にあと1〜2回の追加利上げが、1.0%〜1.5%のレンジに収まるとしています。これは、比較的可能性が高いと見ているシナリオでもあります。
むろん、このタイミングでも米国の関税による景気減速が大きく、利上げが打ち止めとなる可能性は残っています。関税はいったん米国民が負担し、企業の業績には遅れて影響してくるためです。
追加利上げができない場合
2026年度に入っても日銀がほとんど動くことができなければ、単発の小幅引き上げで終了し、政策金利の上限は0.75%にとどまる可能性もあります。
ただし、正常化へ向けての利上げ姿勢を維持している日銀としては、これだけは避けたいと思っているシナリオなので、可能性としては低いです。
日銀利上げシナリオと適合する住宅ローン金利タイプ
住宅ローンをこれから組む人にとって重要なのは、このシナリオがローン選択に直結する点です。
もし「早く利上げを行い、その後は1回程度で頭打ちになる」または「利上げできなくなる」シナリオが現実化すれば、変動金利型の住宅ローンが有利になるでしょう。短期的に金利が動いても、その後は横ばいになるため、低金利の恩恵を受けやすいからです。
反対に、「オンタイムで利上げが行われ、2年以内に2回以上利上げが行われる」または「利上げ開始が遅れ、その後4回以上にわたって金利が積み上がっている」展開になれば、フラット35のような全期間固定型のほうが安心です。長期的な支払いを安定させ、将来の追加利上げのリスクから家計を守れる点が強みになるでしょう。
こうしたシナリオを頭に入れて具体的な金利を見ることで、ご自身の住宅ローン選びの解像度がより上がることと思います。
10月の住宅ローン金利
こうしたシナリオを踏まえたうえで、10月の金利を見てみましょう。
フラット35は横ばい
9月19日発表の機構債(住宅金融支援機構債)※の表面利率は2.12%(前月比+0.04)に上がったため、フラット35の店頭金利も上がる可能性がありましたが、フラット35買取型の金利は1.89%のまま横ばいにとどまりました。
※フラット35は、住宅金融支援機構債という債権を発行して機関投資家に販売することで、資金調達を行っている。
住宅金融支援機構は、金利が過度に上がらないよう必要に応じて調整することがあります。マーケットから見るとかなり割安な金利になっています。
なお、フラット50(50年固定)は、フラット35に+0.10%程度の上乗せで1.99%。超長期でこの水準を固定できるメリットは小さくありません。
【関連記事】>>2025年10月の住宅ローン金利(フラット35、変動金利、10年固定)を予想! 金利の推移、今後の金利動向を確認しよう
ローンチスプレッド拡大:長期資金に“高めの要求利回り”
注目すべきはローンチスプレッド(機構債の表面利率と同時点の10年国債利回りの差)です。2025年春は約0.35%でしたが、現在は0.51%まで拡大しています。
これは、銀行や生命保険会社などの長期投資家が住宅ローン債券に対して、より高い利回りを要求しているサインです。言い換えれば、市場が将来の利上げを先取りしている状況です。
その結果、長期固定型の民間住宅ローンやフラット35の金利は、国債利回りが横ばいでも、相対的に上がりやすい状況が続きます。
民間金融機関の住宅ローン:変動型は横ばい、固定型はじわじわ上がる
10月の変動金利はおおむね横ばい状態です。ただし、みずほ銀行は主要行から約6カ月遅れで調整に入る独自ルールがあり、0.775%(+0.25%)に上がりました。(参考:みずほ銀行の変動金利はなぜ0.15%しか上がらなかったのか? 住宅ローン金利見直しルールのカラクリを解説!)
固定金利(10年・20年・30年)は、ローンチスプレッドの拡大により総じて上昇傾向にあります。8月から9月にかけても金利を上げた銀行が多く、9月から10月はもう一段の上昇がありました。
利上げ時期の本命は12月から来年1月、繰り上げ返済は焦らずに
最後に、現状の繰り上げ返済ですが、現行の低金利下においての効果は薄い状況。変動金利1.3%で50万円を繰り上げたとしても、年あたりの利息軽減は約6,500円にとどまります。もちろん累積効果はありますが、現時点で破綻回避のための借り換えや繰り上げを急ぐ局面ではありません。
不安を和らげるための安心材料として、固定金利や長期固定金利を選ぶ発想は一理あります。しかし、繰り上げ返済の是非は、キャッシュフロー余力、流動性確保、今後の収入不確実性とセットで判断しましょう。
【関連記事】>>住宅ローンの金利推移(変動・固定)は? 最新の動向や金利タイプの選び方も解説
| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[新規借入] |
| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[借り換え] |
 |
 |
| 【金利動向】おすすめ記事 | 【基礎】から知りたい人の記事 |
| 【今月の金利】 【来月の金利】 【2025年の金利動向】 【変動金利】上昇時期は? 【変動金利】何%上昇する? |
【基礎の8カ条】 【審査】の基礎 【借り換え】の基礎 【フラット35】の基礎 【住宅ローン控除】の基礎 |
新規借入2026年1月最新 主要銀行版
住宅ローン変動金利ランキング
※借入金額3000万円、借入期間35年で試算
- 実質金利(手数料込)
- 0.722%
- 総返済額 3387万円
- 表面金利
- 年0.590%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 79,074円
①保証料など0円サービスが充実
②新規借入の場合は自己資金10%以上で金利優遇あり
③最大3億円まで借入可能


![]()
住宅ローン 全期間引下げ(新規借入)・変動金利
- 実質金利(手数料込)
- 0.762%
- 総返済額 3410万円
- 表面金利
- 年0.630%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 79,611円
①低金利の上、がん50%団信無料
②無料で全疾病保償&12カ月の就業不能保償を付帯
③金利+0.1%で、がん100%団信も付帯OK


- 実質金利(手数料込)
- 0.782%
- 総返済額 3421万円
- 表面金利
- 年0.650%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 79,880円
①店舗相談でも、低金利商品あり
②新規借入なら、注文住宅で必要な「つなぎ融資」に対応!
③3大疾病の50%保障が無料付帯!
④無料で、3大疾病50%保障&就業不能保障&就業不能保障を付帯する


-
住宅ローン利用者口コミ調査の詳細を見る
-
今回作成した「住宅ローン利用者口コミ調査」の調査概要は以下のとおり。
【調査概要】
調査日:2023年12月
調査対象:大手金融機関の住宅ローン利用者(5年以内に住宅ローンを新規借り入れ、借り換えした人)
有効回答数:822人
調査:大手アンケート調査会社に依頼
評価対象:有効回答数47以上を対象とするアンケートの設問は以下の7問。回答は5段階評価とした。なお、評価点数の平均点は小数点第2位以降を四捨五入。
【アンケートの設問】
Q1.金利の満足度は?
Q2.諸費用・手数料等は妥当でしたか?
Q3.団体信用生命保険には満足しましたか?
Q4.手続き・サポートには満足しましたか?
Q5.審査について、満足していますか?
Q6.借り入れ後の対応に満足しましたか?
Q7.他の人にも現在の銀行を勧めたいと思いますか?
【回答の配点】
・各設問は5段階で回答してもらい、Q1なら以下のように配点。平均値を求めた。
満足している(5点)
どちらかといえば満足している(4点)
どちらともいえない(3点)
どちらかといえば不満である(2点)
不満である(1点)
・総合評価については、各項目の平均値を全て合算。読者が重視する「Q1金利の満足度」については点数を3倍、「Q3団信の満足度」の点数を2倍として、点数の合計を50点満点とし、10で割ることで5点満点の数値を求めた。
|
保証料や団信などの諸費用がほとんど無料  |
|
132銀行の住宅ローンを比較 >>返済額シミュレーションで、全銀行の金利を一気に比較・調査
|
- 年収に対して安心して買える物件価格は?
-
- ・年収200万円で妻が妊娠中の家族の上限は1600万円!?
- ・年収250万円の単身者の上限は1800万円!?
- ・年収300万円の4人家族の上限は1800万円!?
- ・年収350万円の2人家族の上限は2100万円!?
- ・年収400万円の単身者の上限は2500万円!?
- ・年収450万円の4人家族の上限は2000万円!?
- ・年収500万円の4人家族の上限は3000万円!?
- ・年収600万円の3人家族の上限は3500万円!?
- ・年収600万円の40代独身の上限は3000万円!?
- ・年収700万円の共働き夫婦の上限は5000万円!?
- ・年収800万円の3人家族の上限は4500万円!?
- ・年収1000万円の30代4人家族の上限は5000万円!?
- ・年収1000万円の40代4人家族の上限は3500万円!?
- ・年収1000万円の50代夫婦の上限は3000万円!?
※サイト内の金利はすべて年率で表示







 関連記事
関連記事

プロの評判・口コミ
淡河範明さん
SBI新生銀行の住宅ローンは、10年固定、15年固定、20年固定といった金利が低い点が特徴です。
商品も特徴的で、介護状態を保障する団信や、長く借りていると金利が下がっていく「ステップダウン金利」があるのも主要銀行ではここだけです。
審査はオーソドックスに行なっている感じです。住宅ローン処理センターで集中審査しているので、窓口のかたの力量があまり問われず、公平に審査されるという印象です。
なお、相談から審査、契約の手続きまでネットで完結できるようになりました。不安な方には、ビデオ通話で自宅から気軽に相談ができるので、コロナ禍の現状では最適な方法が用意されているようです。