個人事業主や法人が事業資金を調達するときに、「不動産担保ローン」という融資があります。所有している不動産を担保にして融資を受けるものですが、どんな不動産でもよいわけではありません。今回は、不動産担保ローンでよくあるトラブル、契約の際の注意点を紹介します。住宅ローンや不動産投資のローンにも共通する部分がありますので、参考にしてください(金融ライター・加藤隆二、現役銀行員)。
銀行員が見た不動産担保ローンのトラブル

個人事業主や法人が事業資金を調達するために、所有している不動産を担保にして融資を受けるのが「不動産担保ローン」です。不動産担保ローンは会社員など一般の人でも、担保にできる不動産があれば利用できます。
なお、担保とは「将来に発生するかもしれない不利益に対し、それを補うための事物(モノ)」のことです。「抵当」とも呼ばれ、ここから抵当権・根抵当権という言葉も生まれました。
ではここから、不動産担保ローンで担保にする不動産の内容や、担保の手続きなどで発生する問題をいくつか紹介します。銀行員にとっては担保手続きではよく発生する「トラブル」なのですが、お客様はほとんどの人が初体験なので焦ります(もちろん「大丈夫ですよ」とフォローはしますが)。いざ問題に直面したときに焦らないで済むよう、ぜひ参考にしてください。
【関連記事はこちら】>>【銀行員が解説】住宅ローンなどで担保評価が低くなってしまう不動産とは? 物件選びでは「売れない不動産」は避けよう!
不動産担保ローン【小トラブル】自分の名前や住所が書けない
不動産担保ローンの手続きや契約書類では、原則として住民票に記載されている通りの氏名と住所で記入することになっています(これは住宅ローンや不動産投資ローンも同様です)。ところが中には「自分が普段意識して使っている住所や氏名が住民票では違っていた」というケースがあります。
まず住所ですが、住民票の住所地で一般的な住居表示以外に「字」(*)が入っていたり、住居表示以前で「1丁目」などがなく番地も住所と違っていたり、あるいは住所に使われている漢字が旧字体だったりといったケースです。これは明治期などに住所地を再編製した際、従来とは違う集計方法になったために、微妙に数字が違う場合があることが原因です(ちなみに戸籍では地番を使うのが一般的です)。また住居表示と一緒でも「〇〇町1−2−3」という住所なら住民票では「〇〇町1丁目2番3号」と表記されていて、その通りに記入しなければなりません。
たとえば私の家を例にとると、以下の通り微妙に違います(多少変更しています)。
【普段使う住所】 〇〇市沢田町1-2-34
【住民票の住所】 〇〇市沢田町1丁目2番34号
【地番(本籍)】 〇〇市澤田町1丁目1458
またこれは、氏名でも起こることで、たとえば渡辺の「辺」は「邉」「邊」などいくつもありますし、高橋でも「高」と「髙」、「橋」と「槗」「𣘺」などがあります。他にも「澤田(沢田)」「山崎(山﨑、山嵜)」など例をあげるときりがありません。日常生活ではいわゆる常用漢字の字体にして「澤田⇒沢田」で支障なく過ごせるのですが、これが融資の契約や担保の書類になると、住民票で登録された字体を使う必要があります。
そのためお客様の中には、そこで初めて自分の「正式名称」を知ったという人もいます。そして、普段は書き慣れていない自分の名前や住所を記入するのに苦労する、ということがよくあります。(私の場合、こうしたケースでは書類を記入する前に、数回試し書きをしてもらうようにしています)。
*字・あざ:昔の村単位を「大字」、その中の集落単位を「字」として住所として変遷してきた。その後市町村合併した場合は以前の村や集落を表した。
例)「山田村海田」⇒(市町村合併)⇒「〇〇市大字山田字海田」
不動産担保ローン【小トラブル】権利書がない!
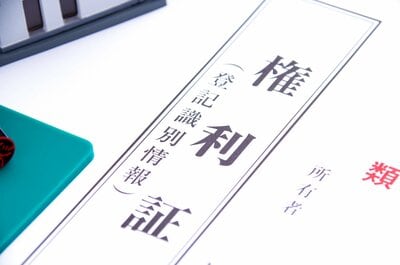
土地や建物を自分が所有していることを証明するのが「権利書(権利証ともいう)」です。ところがこの権利書は結構やっかいで、契約直前や手続きの当日になって「権利書がない!」とお客様から言われることがよくあります。これは、一般の人は日常生活で権利書に触れることなどまず無いということと、大事な書類なので「仏壇の上から2番目の引き出しにある」と考えるだけで、普段はそのありかを確かめたりしないことが大きな原因です。
ところが、
「仏壇にあると思っていたのに探しても見つからなかった」
「権利書だと思っていたら、全く別の書類だった」
といったようなケースは、銀行員からすればまさに日常茶飯事で、私も何度か困った経験があります。その苦い経験から、今はたとえば住宅ローンで審査が通った段階で、権利書を探しておいてもらうようにしています。一度探してもらえば、「ちゃんと保管しているか?」「なくなっているのか?」もわかりますし、事前に見せてもらえば目的の権利書かどうかも確認できるからです。
ちなみに権利書がなくなってしまっていても、所有者本人の身分証明と書類などで手続きはできますが、余計な時間と費用がかかります。また現在は権利書自体がなくなり、データを法務局に電子記録することで登記ができるようになっています。そして権利書の代わりに電子記録された証明として「登記識別情報通知」という書類が発行される形です。(大事な書類である点は変わりませんが、記録がオンライン化されているので、登記識別情報通知をなくしても、所有者の本人確認などで手続きはできます)
不動産担保ローン【中トラブル】あるはずの土地がない
これはケースとして多くはないのですが、自分たちの不動産が自分や家族が考えていた通りではなかったという事例です。
1. 先祖から引き継ぎ親名義の土地だと思っていた場所が、実は他人の所有地だった
2. 担保にしようとした土地の真ん中に、知らない人名義の土地が存在していた
3. 所有地と道路の間に他人の土地があり、自分の土地は道に接していないことが判明した
これらはすべて、私が銀行員として実際に経験した事例です。どれも一大事で、それこそ銀行と取引している場合ではない事態でした。
1のケースは単なる番地の勘違いで、すぐ隣にしっかり土地があったので問題なく手続きできました。
2のケースでは、土地を所有する人と連絡が取れず担保にもできなかったので、融資ができませんでした。
3のケースでは相手名義の土地を購入するか、相手から担保に提供してもらう必要がありました。しかしそのどちらも納得してもらえず(いきなり土地を売れ、土地を担保に出せと言われたら、私でも断ると思います)融資ができなかっただけでなく、そのあとも相手ともめることになってしまいました。
ここで紹介した事例も、銀行員からすれば「トラブル」のケースなのですが、とはいえ一般の人が自分の土地について調べるのは、誰かが死んで相続するとき、売却するとき、そして借金の担保にするときくらいですので、こういったハプニングも発生するのだと銀行員の私は思います。今は特に問題がなくても、事実が判明すると大騒ぎになることも多いので、機会があるとき(法事や帰省時など家族がそろうタイミング)に、家族みんなで確認しておくことをおすすめします。
不動産担保ローン【中トラブル】土地所有者がお年寄りで字が書けない
「字が書けない」というケースは、銀行取引全般に関連し、特に住宅ローンや不動産担保ローンでも手続きが進まなくなる「トラブル」です。不動産担保ローンや住宅ローンなどでは、担保にする不動産の所有者は本人以外、たとえば父母・祖父母・曽祖父母名義でも構いません。ただし自分以外の場合、たとえば祖父、祖母、あるいは父母が高齢で字が書けないと手続きが大変になります。
不動産担保ローンでも住宅ローンでも、担保となる不動産の所有者(担保提供者)は、融資の契約書類や担保書類に自署捺印する必要があります。しかし、普段の生活で自分の親や祖父母に担保契約書類を書かせることなど、一般人は想像すらしないことなので、こうした問題が発生するのです。
繰り返しになりますが、担保の契約書類や登記に必要な書類は、所有者が担保に提供することをしっかりと理解し納得した証明として、本人の自署が大前提です。したがって、字がヨレヨレになる程度なら、時間がかかっても本人にゆっくり書いてもらえば手続きできます。また字がまったく書けない(手が震えるなど)場合でも、本人が元気で会話もできれば「代筆(家族のうち誰か一人が代わりに書くこと)」も可能です。ただし代筆で契約してもらえるか?は金融機関によっても対応が違うので、断られる可能性もあります。
また認知症などで意思が通じない、あるいは会話ができない場合には、「そもそも担保を提供することに納得しているか?」が確認できないので手続きができない、つまり融資が受けられないことになります。
ちなみに高齢で意思疎通が難しい人には「成年後見人」という制度がありますが、基本的に本人(祖父など)の財産や利益を守る行為しか認められない、というのが大原則です。したがって「子や孫の借金に担保を差し出す(子や孫の利益であり、本人にとっては不利益)」のはまず無理なので、ここはぜひ覚えておいてください。
私の場合、融資申し込み段階で上記のような事態になったなら、担保の所有者を成年後見人にするか悩んでいるお客様には、成年後見人になると原則として担保提供できないことを説明したうえで、高齢者本人や家族の今後について慎重に考えてもらうようにしています(成年後見制度を利用するかどうかは本人や家族の問題であって、銀行員から指図するようなことはありません)。
不動産担保ローン【大トラブル】貸している人が邪魔する
不動産担保ローンは自宅以外の遊休地を担保にするケースが多いので、そうなると他人に貸している借地や借家などが担保になることもあります。しかしその場合に、借家が未登記ということがあります(借りている土地はいつか返さなければいけないからと、建物を建てても登記しない人がいるから)。
建物が未登記では銀行で担保と認めてもらえないので、地主は建物所有者の借地人(土地を貸している人)に「建物の登記をしてくれ」と頼むのですが、地主の都合に付き合って登記をしてくれる人は少ないのが現実です(登記費用を地主が持つからと解決したケースはありました)。
このようなトラブルを防ぐため、担保にすることをきっかけとして借地人に「出ていってくれ」と頼む地主もいます。しかし、地主の事情を知り、金銭を得ようと考えて居座る人もいるので、こうなると担保にするのは無理になってしまいます。
現在は借地人や借家人といった「土地や家を借りている人」の権利を守るべきだ、として法律も整備されているので、話がこじれると訴訟に発展してしまう可能性もあります。基本的に銀行はトラブルなどを嫌うので「もめているならこのお話はなかったことに」と手を引くかもしれません。このように、自分の土地であっても「他人に貸しているなら半分は他人に権利がある」くらいの意識で考えた方がいいという事例です。
不動産担保ローン【大トラブル】担保と認めてもらえない
これは土地や建物など物件に問題があるケースで、担保にしてもらえなければ融資を受けることもできないので、問題は大きいといえます。
・担保調査で、土地に道路がつながっていないことが判明した
(建物が建てられない無道路地となり売れないので、銀行は担保にしない)
・数年後には道路(計画道路)の一部になることが本決まりで担保にできないと言われた
(売却できるのが大前提、道路になる土地を担保に金を貸す金融機関はない)
・建物が容積率を超過していて、一部または全部を取り壊さなければ担保にできない
(建ぺい率や容積率を超えている建物は、是正しなければ銀行では担保にしない)
ここで紹介したのはほんの一例で、その他にも銀行で担保と認めてくれない物件は何種類もありますが、基本的には「売却できるか?」「自分ならその土地に住みたいと思うか?」とイメージしてみるとわかりやすいと思います。なお不動産担保ローンは不動産の評価額を重視するため、担保にできる物件は金融機関によって条件が異なりますので、必ずご自身で確認してください。
【関連記事はこちら】>>【銀行員が解説】最近の住宅ローン担保評価、融資可能額はどう計算しているのか?
不動産担保ローンフロー(申し込みから手続きまで)
最後に、不動産担保ローンの申し込みから担保手続きまでのフローを簡単にまとめました。ここまでに解説した問題点や注意点をイメージすると吸収しやすいと思います。また基本的な流れは住宅ローンや不動産投資ローンも同じなので、参考にしてください。
フロー1.申し込み・審査
最近は不動産担保ローンもネット経由の申し込みが主流になりつつあります。申し込みに必要な主な書類は以下の通りです。
・ローン借入申込書兼同意書
・資金の使用用途が分かる資料
・源泉徴収票、年金振込通知書など収入関連書類
・固定資産税納税証明書
・住民税納税証明書
・運転免許証など本人確認資料
なお、申し込みに必要な書類は公式ページで告知している銀行もあります。
【参考】東京スター銀行/「スター不動産担保ローン」必要書類チェックリスト
フロー2.担保調査と評価、融資の審査
銀行や消費者金融などの担当者が、担保予定の現地に行って写真撮影や現地調査をします。
評価については、一般に「土地の相場は路線価の1.2倍、銀行の評価は路線価の6割程度⇒相場の半分程度」といわれています。
例)
・土地の路線価(*)が1億円なら、相場は1.2倍の1億2千万円
・銀行の評価は路線価の6割で6千万円なので、相場の半分
上記はあくまで俗説で、実際に銀行が路線価に対してどのくらいの評価をするかは部外秘でいえませんが「当たらずしも遠からず」といったところでしょうか。
そして次に、不動産担保ローンの審査では決算内容と担保の評価を中心に審査をします。ちなみに「不動産担保ローン 審査なし」「絶対に借りれる不動産担保ローン」といった記事を見受けますが、審査のない不動産担保ローンはありません。実際これらの記事も「審査のない不動産担保ローンはありませんが、その中でもこちらを」と結局は見出しで釣っておいて特定のローンなどに誘導する内容が多いので注意してください。
フロー3.借入契約と担保の登記
融資契約書類に借り入れする本人と、担保の所有者(担保所有者)が自署・捺印して契約が進みます。また最近では契約もネットで完結するなど、手続きが簡素化されています。このようにお金を借りる融資契約は簡単になりましたが、担保契約に必要な書類は昔とあまり変わっていません。
参考に、担保の契約書類として必要な書類は主に以下のとおりです。
<担保契約に必要な書類>
1. 担保契約書類(抵当権設定契約書など)
2. 土地・建物の登記済権利証または「登記識別情報通知」
3. 土地・建物所有者の印鑑証明書や住民票(発行日から3ヶ月以内)
また登記の実務手続きは専門家の司法書士に委任するのが一般的なので、そのための登記費用を支払うことになります。担保の登記は税金としての収入印紙代と、事務手続きの費用として司法書士に報酬があり、金額は数万円〜数十万円です。担保金額が多ければ印紙代が上がり、担保になる不動産の個数が増えても金額が大きくなります。
そして、ここまでの担保契約が無事終了すれば、借り入れを利用できることになります。
まとめ
今回は不動産担保ローンで担保にする不動産について、さまざまな問題や注意点を解説してきました。基本的に担保やその手続きは住宅ローンや不動産投資ローンも同様なので、この記事で述べたことが参考になれば幸いです。
| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[新規借入] |
| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[借り換え] |
 |
 |
| 【金利動向】おすすめ記事 | 【基礎】から知りたい人の記事 |
| 【今月の金利】 【来月の金利】 【2025年の金利動向】 【変動金利】上昇時期は? 【変動金利】何%上昇する? |
【基礎の8カ条】 【審査】の基礎 【借り換え】の基礎 【フラット35】の基礎 【住宅ローン控除】の基礎 |
新規借入2026年1月最新 主要銀行版
住宅ローン変動金利ランキング
※借入金額3000万円、借入期間35年で試算
- 実質金利(手数料込)
- 0.722%
- 総返済額 3387万円
- 表面金利
- 年0.590%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 79,074円
①保証料など0円サービスが充実
②新規借入の場合は自己資金10%以上で金利優遇あり
③最大3億円まで借入可能


![]()
住宅ローン 全期間引下げ(新規借入)・変動金利
- 実質金利(手数料込)
- 0.762%
- 総返済額 3410万円
- 表面金利
- 年0.630%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 79,611円
①低金利の上、がん50%団信無料
②無料で全疾病保償&12カ月の就業不能保償を付帯
③金利+0.1%で、がん100%団信も付帯OK


- 実質金利(手数料込)
- 0.782%
- 総返済額 3421万円
- 表面金利
- 年0.650%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 79,880円
①店舗相談でも、低金利商品あり
②新規借入なら、注文住宅で必要な「つなぎ融資」に対応!
③3大疾病の50%保障が無料付帯!
④無料で、3大疾病50%保障&就業不能保障&就業不能保障を付帯する


-
住宅ローン利用者口コミ調査の詳細を見る
-
今回作成した「住宅ローン利用者口コミ調査」の調査概要は以下のとおり。
【調査概要】
調査日:2023年12月
調査対象:大手金融機関の住宅ローン利用者(5年以内に住宅ローンを新規借り入れ、借り換えした人)
有効回答数:822人
調査:大手アンケート調査会社に依頼
評価対象:有効回答数47以上を対象とするアンケートの設問は以下の7問。回答は5段階評価とした。なお、評価点数の平均点は小数点第2位以降を四捨五入。
【アンケートの設問】
Q1.金利の満足度は?
Q2.諸費用・手数料等は妥当でしたか?
Q3.団体信用生命保険には満足しましたか?
Q4.手続き・サポートには満足しましたか?
Q5.審査について、満足していますか?
Q6.借り入れ後の対応に満足しましたか?
Q7.他の人にも現在の銀行を勧めたいと思いますか?
【回答の配点】
・各設問は5段階で回答してもらい、Q1なら以下のように配点。平均値を求めた。
満足している(5点)
どちらかといえば満足している(4点)
どちらともいえない(3点)
どちらかといえば不満である(2点)
不満である(1点)
・総合評価については、各項目の平均値を全て合算。読者が重視する「Q1金利の満足度」については点数を3倍、「Q3団信の満足度」の点数を2倍として、点数の合計を50点満点とし、10で割ることで5点満点の数値を求めた。
|
保証料や団信などの諸費用がほとんど無料  |
|
132銀行の住宅ローンを比較 >>返済額シミュレーションで、全銀行の金利を一気に比較・調査
|
- 年収に対して安心して買える物件価格は?
-
- ・年収200万円で妻が妊娠中の家族の上限は1600万円!?
- ・年収250万円の単身者の上限は1800万円!?
- ・年収300万円の4人家族の上限は1800万円!?
- ・年収350万円の2人家族の上限は2100万円!?
- ・年収400万円の単身者の上限は2500万円!?
- ・年収450万円の4人家族の上限は2000万円!?
- ・年収500万円の4人家族の上限は3000万円!?
- ・年収600万円の3人家族の上限は3500万円!?
- ・年収600万円の40代独身の上限は3000万円!?
- ・年収700万円の共働き夫婦の上限は5000万円!?
- ・年収800万円の3人家族の上限は4500万円!?
- ・年収1000万円の30代4人家族の上限は5000万円!?
- ・年収1000万円の40代4人家族の上限は3500万円!?
- ・年収1000万円の50代夫婦の上限は3000万円!?
※サイト内の金利はすべて年率で表示







 関連記事
関連記事

プロの評判・口コミ
淡河範明さん
SBI新生銀行の住宅ローンは、10年固定、15年固定、20年固定といった金利が低い点が特徴です。
商品も特徴的で、介護状態を保障する団信や、長く借りていると金利が下がっていく「ステップダウン金利」があるのも主要銀行ではここだけです。
審査はオーソドックスに行なっている感じです。住宅ローン処理センターで集中審査しているので、窓口のかたの力量があまり問われず、公平に審査されるという印象です。
なお、相談から審査、契約の手続きまでネットで完結できるようになりました。不安な方には、ビデオ通話で自宅から気軽に相談ができるので、コロナ禍の現状では最適な方法が用意されているようです。