全半壊約40万戸の被害をもたらした東日本大震災。当然、その中には住宅ローンを支払っている最中の建物も多く、そこで問題になるのが、被災者の抱えるローン(被災ローン)だ。自宅がなくなったにもかかわらず、多額の住宅ローンだけが残ったり、自宅再建のために新たにローンを組むことでローンが多重化したりすれば、下手をすれば家計が破綻するかもしれない。いわゆる被災ローンの問題は、住宅ローンを抱えている人にとっては他人事ではなく、漠然とした不安を抱いている人も多いだろう。東日本大震災の被災地での現地取材もまじえて、被災しても住宅ローンで人生を台無しにしないためのポイントを紹介していきたい。(ジャーナリスト・木野龍逸)
| ◆連載「震災で、住宅ローンだけが残ったらどうなる?」 | |
| ・ | 【第1回】返済が苦しければ、私的整理ガイドラインで減免を |
| ・ | 【第2回】 申し込んでも、債務免除できたのはわずか4分の1 ! |
| ・ | 【第3回】 災害の規模が大きいほど、後から支援策が出る?! |
| ・ | 【第4回】 50%しか補償できない地震保険で不安なら? |
 東日本大震災の津波による被害、宮城県仙台市(出所:消防科学総合センター)
東日本大震災の津波による被害、宮城県仙台市(出所:消防科学総合センター)2011年3月11日に発生した東日本大震災。マグニチュード9.0という巨大なエネルギーから生まれた揺れと、それによって発生した津波により、全半壊約40万戸という未曽有の被害をもたらした。
仙台弁護士会が震災直後から取り組んだ法律相談には、窮状を訴える人が相次いだ。
「震災当日に引き渡しを受けた新築住宅が津波で流失して住宅ローンだけが残った」
「津波で家を失って賃貸住宅に入ったが、既存ローンの上に賃料が発生して生活が成り立たない」
「事業用資産が流されてしまい、既存ローンを抱えながらどうしていいのかわからない」
東日本大震災の被害総額は、内閣府が2011年6月24日に約16兆9000億円と推計しているが、6年が経過した今も被災地は復旧途上にあり、9万人以上が避難生活を送っていることなどを考えると、全容はなお明らかになっていないと言える。
こうした中、1995年に発生した阪神・淡路大震災の後にも問題になった、住宅の「二重ローン」をはじめとする、いわゆる「被災ローン」が被災者を苦しめている。
長期の住宅ローンが一般化している日本では、災害によって自宅がなくなったにもかかわらず、多額のローンだけが残ったり、自宅再建のために新たにローンを組むことでローンが多重化することが、起こりやすい。
災害時には被災者生活再建支援法による住宅再建などのための給付金(最大300万円)は出るが、大きく壊れた家を修復、あるいは解体後に新築するにはあまりにも不十分だ。災害時の低利融資制度もあるが、結局は債務を増やすことになるので、被災者の負担軽減にはなりにくい。
通常、処分する財産がなくなり、住宅ローンの支払いもできなくなった場合、考えられるのは自己破産だろう。自己破産が認められれば、住宅ローンは大きく減免される。しかし、自己破産は本人にとってダメージが大きく、立ち直るにも時間がかかる。本人だけでなく、地域経済の復旧にも大きな影を落とすことになる。
では、大規模災害に巻き込まれたらどうすればいいのか。東日本大震災で頼みの綱として期待されたのが、支払いに苦しんでいる人の被災ローンを減免できる制度、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」(個人版ガイドライン)だ。
東日本大震災では1300人以上が、
個人版ガイドラインによりローンを減免
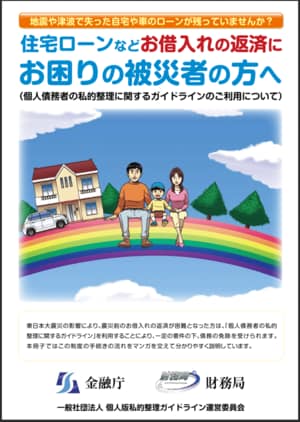 個人版ガイドラインには、手続きの流れ(マンガ版)も用意されている(個人版ガイドライン運営委員会サイトから引用)
個人版ガイドラインには、手続きの流れ(マンガ版)も用意されている(個人版ガイドライン運営委員会サイトから引用)個人版ガイドラインは、金融庁の下に設置された研究会によって、地震発生から4カ月後の2011年7月に策定された。実際の運用は同年8月22日に始まった。減免の対象になるのは、住宅ローン、自動車ローン、事業に係る債務などさまざまなものを含む。
個人版ガイドラインを利用してローンの減免ができたのは、2017年2月24日時点で1351件だった。運営委員会のホームページでは、12の成立事例が紹介されていた(現在は掲載終了)。ここでは、3つの事例を見てみよう。
例えば、東日本大震災で自宅が全壊し、みなし仮設住宅に居住している男性は、「一時的に猶予されている住宅ローンの返済が再開され、さらに仮設を退去するとアパート代が発生することになると大変だ。収入は安定しているのだが、住宅ローンとアパート代を両方払うことになれば、返済が困難になるのは明らかだ」と考えて個人版ガイドラインに申し込んだ。下表はその結果だ。
| 住宅ローンの7割が免除で、手元に500万円残る! 個人版ガイドライン活用した人の資産・ローンの推移(同運営委員会の事例を元に作成) |
|
| 当初(仮設住宅を退去したら、支払いが困難になる) | |
| 住宅ローン残高 | 3270万円 |
| 預貯金 | 約1500万円 |
| ↓ ↓ ↓ | |
| ガイドラインを活用して免除 | |
| 返済(自宅跡地買上げ代金) | 165万円 |
| 返済(預貯金の一部) | 970万円 |
| 残りの住宅ローンは免除 | 2135万円 |
| 預貯金 | 500万円 |
| ↓ ↓ ↓ | |
| 免除後も資産を持てる | |
| 預貯金(手元に残せた自由財産) | 500万円 |
上表の通り、被災ローンは住宅ローンの3270万円だったが、自治体による自宅跡地買上げ代金165万円と、現預金の一部970万円を返済することで、残りの住宅ローン2135万円が免除されたという。手元には自由財産として500万円を手元に残しながら住宅ローンを精算できたので、生活再建もある程度スムーズに行きそうだ。
津波で自宅が流出し、仮設住宅に居住している福島県の男性は、震災で収入が減少し、今後仮設住宅を出る時に新たな家賃負担が発生することに不安を感じていた。そこで債務整理について相談し、住宅ローン2000万円について、自宅跡地を売却して得られた100万円を一括で返済し、残りの1900万円の免除を受けることができたという。
ほかにも住宅ローンと自動車ローンを合わせて2000万円あった被災ローンのうち、600万円を一括返済した残りの1400万円を免除された例などがある。
このように、住宅ローンの大半を債務免除してもらえる可能性があるのだ。
500万円+義捐金を手元に残せるほか、
債務整理後にすぐ、新たなローンを借りられる
個人版ガイドラインの特徴は第1に、法的整理、つまり裁判所で行う破産手続きによらずに債務の整理ができることだ。破算と同等か、それよりも多く返済できる計画案を示し債権者の同意が得られれば、被災ローンが減免される。破産以上の返済を求められるのはハードルが高いように思えるかもしれないが、すでに返済が相当厳しい状況であれば、破産であっても、個人版ガイドラインによる債務整理であっても、返済できる額はそれほど変わらないだろう。なお、被災者にとってメリットがあるだけでなく、ある程度の債務放棄をする債権者にとっても、債務者が個人破産するよりも多くのお金が回収できる可能性がある。
第2の特徴は、法的整理とは違って信用情報がブラックリストに載らないため、債務整理後にすぐ、生活再建に向けた新たなローンを組めることだ。お金が回るようになるのは、銀行にとっても悪い話ではないだろう。
第3の特徴は、債務整理後に手元に残して自由に使える財産の上限が、法的整理では99万円なのに対し、個人版ガイドラインでは500万円になっていることだ。個人版ガイドラインの開始当初は法的整理と同じ99万円だったが、その後、裁判で自由財産の幅が広がる判決が出たことなどで、500万円に引き上げられた。義援金などはこの500万円の枠には入らないので、自由財産の枠はさらに拡張される。
このほかにも、災害時の被災者支援に携わっている津久井進弁護士は、著書「大災害と法」(岩波新書)の中で個人版ガイドラインについて、債務者だけでなく連帯保証人も制度を利用できるために両者が救済される余地があることや、申し込みをすると登録専門家(弁護士や税理士、会計士など)を紹介されて、無料で債権者との交渉にあたってくれることなどを特徴として挙げている。専門家の費用は全額、国が負担する。被災ローンを抱えた人にとって、非常にありがたいことだ。
個人版ガイドラインを利用する場合、まずは債権者(銀行)に協議開始の相談をする。この際、個人版ガイドライン運営委員会(以下、運営委員会)を経由して申し込みをすると、運営委員会に登録している弁護士や公認会計士、税理士などの登録専門家が紹介され、協議開始の申し入れ、財務状況の整理、返済計画策定などの支援をしてもらえる。
被災ローンを抱えている人たちにとって個人版ガイドラインは、将来への希望をつなぐ制度といえた。現在でも、東日本大震災を対象に運用が続いている。
今後の自然災害の影響で返済に困ったら、
自然災害ガイドラインで債務整理を検討すべき
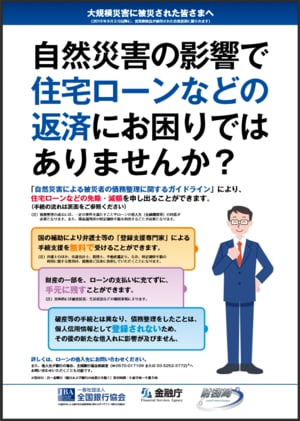 自然災害ガイドラインのチラシ(全国銀行協会サイトより引用)
自然災害ガイドラインのチラシ(全国銀行協会サイトより引用)一方、全国銀行協会(全銀協)は、個人版ガイドラインを改定する形で恒常的に利用できる制度を模索し、2015年12月に、地震に限らず幅広い災害を対象にした「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(自然災害ガイドライン)を策定した。今後の大規模災害は、こちらのガイドラインが適用される。
自然災害ガイドラインが対象にしているのは、15年9月以降に災害救助法の適用を受けた大規模災害だ。これまでに、15年には台風18号と、台風21号の被害、16年は熊本地震と鳥取県中部地震、台風10号の被害が対象になった。16年12月に発生した新潟県糸魚川の大規模火災も、自然災害ではないが災害救助法が適用されたために、制度の対象になっている。
自然災害ガイドラインで減免される被災ローンの内容は、個人版ガイドラインとほとんど同じだ。熊本地震の対応にあたっている熊本県弁護士会はホームページで、自然災害ガイドラインは自己破産などと比べてメリットがあるとしており、①ブラックリストに載らない、②最大500万円の現金と最大250万円の家財保険金のほか災害弔慰金や義援金などを手元に残すことができる、③原則として保証人への支払い請求がされない、の3点を挙げている。
債務整理するには、まず最大の借入先に行き、
同意書をもらった上で、弁護士などと相談を
自然災害ガイドラインを利用する場合、まずは自分で、借り入れしている元金がもっとも大きい銀行に制度の利用を伝えて同意書を発行してもらい、全銀協に対して、登録支援専門家に委嘱して書類作成をしてもらうよう依頼をする。この場合、登録支援専門家の費用は無料だ(書類提出のための郵送料などの実費は別)。
全銀協から弁護士会などを通して委嘱を受けた登録専門家は、債務者と調停案を策定。全債権者に申し出をして、同意が得られれば簡易裁判所に特定調停を申し立て、調停案を確定させる。全債権者への申し出から特定調停による確定までは半年程度かかると予想されている。東日本大震災のときとは若干手続きが違うが、中身はほぼ一緒だ。
熊本県弁護士会によれば、熊本地震に関連した自然災害ガイドラインの利用申し出は、17年1月13日時点で556件だった。これは弁護士会に委嘱があった件数なので、銀行への相談件数はそれよりも多いと思われる。
そして、このうち特定調停が成立したのは、自身も登録支援専門家に登録して被災者支援にあたっている熊本県弁護士会の鹿瀬島正剛弁護士によれば、「20件弱」だという。全銀協もまだ件数を公表していないが、申し出から半年程度かかることを考えると、数が増えるのはこれからになりそうだ。
鹿瀬島弁護士は、「銀行がこの制度を知らないと、リスケジュールを進めるのが普通です。そうなる前にまずは銀行や、災害時の無料法律相談でガイドラインの相談をしてほしい」と、制度の利用を呼びかけている。
リスケジュールで何とかなればいいのだが、それでは返済が相当苦しいという場合は、自然災害ガイドラインを使ったほうがいい。東日本大震災のときは、地震後4カ月は個人版ガイドラインは存在しなかったし、個人版ガイドラインができた後も、知らない銀行員は多かった。さすがに、その反省もあって、最近は銀行員が自然災害ガイドラインを知らないということは減ってきたが、借り手側からもガイドラインの話をすべきだろう。
ローン減免はムシがよすぎるとは考えず、
状況が厳しいと判断したらまずは銀行に相談を
自然災害の被害から立ち直るために、まずは自分でなんとかしようと頑張るのは自然なことだ。しかし被災ローンを抱えれば間違いなく生活再建が遅れるだけでなく、多重ローンによって負の連鎖が生まれるおそれもある。
前述したように被災ローンの減免制度は、最悪の事態を避け、地域経済の早期復旧を目指すために作られた枠組みだ。決して、個人のわがままで借金から逃れるという都合のいい制度ではない。見方を変えれば、貸し手である金融業界も合意の上で成立した、借り手の権利のようなものといえる。
日本では、国が持ち家政策を進めてきた一方、地震多発国での長期ローンのリスクは借り手が背負う形になっているのが現実だ。これに対して、個人版ガイドラインや自然災害ガイドラインは、銀行にも応分のリスク負担を求めるものといえるだろう。
被災時にローンの減免を求めるのはムシがよすぎるのではないかと考えず、状況が厳しいと判断したらまずは銀行に相談してみるのが、生活再建の第一歩ではないだろうか。
次回は、福音とも思えた「個人版ガイドライン」にも意外な落とし穴があることと、その対策も含めて解説したい。
連載「震災で、住宅ローンだけが残ったらどうなる?」
【第1回】返済が苦しければ、私的整理ガイドラインで減免を
【第2回】申し込んでも、債務免除できたのはわずか4分の1!
【第3回】 災害の規模が大きいほど、後から支援策が出る?!
【第4回】50%しか補償できない地震保険で不安なら?
| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[新規借入] |
| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[借り換え] |
 |
 |
| 【金利動向】おすすめ記事 | 【基礎】から知りたい人の記事 |
| 【今月の金利】 【来月の金利】 【2025年の金利動向】 【変動金利】上昇時期は? 【変動金利】何%上昇する? |
【基礎の8カ条】 【審査】の基礎 【借り換え】の基礎 【フラット35】の基礎 【住宅ローン控除】の基礎 |
新規借入2026年1月最新 主要銀行版
住宅ローン変動金利ランキング
※借入金額3000万円、借入期間35年で試算
- 実質金利(手数料込)
- 0.722%
- 総返済額 3387万円
- 表面金利
- 年0.590%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 79,074円
①保証料など0円サービスが充実
②新規借入の場合は自己資金10%以上で金利優遇あり
③最大3億円まで借入可能


![]()
住宅ローン 全期間引下げ(新規借入)・変動金利
- 実質金利(手数料込)
- 0.762%
- 総返済額 3410万円
- 表面金利
- 年0.630%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 79,611円
①低金利の上、がん50%団信無料
②無料で全疾病保償&12カ月の就業不能保償を付帯
③金利+0.1%で、がん100%団信も付帯OK


- 実質金利(手数料込)
- 0.782%
- 総返済額 3421万円
- 表面金利
- 年0.650%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 79,880円
①店舗相談でも、低金利商品あり
②新規借入なら、注文住宅で必要な「つなぎ融資」に対応!
③3大疾病の50%保障が無料付帯!
④無料で、3大疾病50%保障&就業不能保障&就業不能保障を付帯する


-
住宅ローン利用者口コミ調査の詳細を見る
-
今回作成した「住宅ローン利用者口コミ調査」の調査概要は以下のとおり。
【調査概要】
調査日:2023年12月
調査対象:大手金融機関の住宅ローン利用者(5年以内に住宅ローンを新規借り入れ、借り換えした人)
有効回答数:822人
調査:大手アンケート調査会社に依頼
評価対象:有効回答数47以上を対象とするアンケートの設問は以下の7問。回答は5段階評価とした。なお、評価点数の平均点は小数点第2位以降を四捨五入。
【アンケートの設問】
Q1.金利の満足度は?
Q2.諸費用・手数料等は妥当でしたか?
Q3.団体信用生命保険には満足しましたか?
Q4.手続き・サポートには満足しましたか?
Q5.審査について、満足していますか?
Q6.借り入れ後の対応に満足しましたか?
Q7.他の人にも現在の銀行を勧めたいと思いますか?
【回答の配点】
・各設問は5段階で回答してもらい、Q1なら以下のように配点。平均値を求めた。
満足している(5点)
どちらかといえば満足している(4点)
どちらともいえない(3点)
どちらかといえば不満である(2点)
不満である(1点)
・総合評価については、各項目の平均値を全て合算。読者が重視する「Q1金利の満足度」については点数を3倍、「Q3団信の満足度」の点数を2倍として、点数の合計を50点満点とし、10で割ることで5点満点の数値を求めた。
|
保証料や団信などの諸費用がほとんど無料  |
|
132銀行の住宅ローンを比較 >>返済額シミュレーションで、全銀行の金利を一気に比較・調査
|
- 年収に対して安心して買える物件価格は?
-
- ・年収200万円で妻が妊娠中の家族の上限は1600万円!?
- ・年収250万円の単身者の上限は1800万円!?
- ・年収300万円の4人家族の上限は1800万円!?
- ・年収350万円の2人家族の上限は2100万円!?
- ・年収400万円の単身者の上限は2500万円!?
- ・年収450万円の4人家族の上限は2000万円!?
- ・年収500万円の4人家族の上限は3000万円!?
- ・年収600万円の3人家族の上限は3500万円!?
- ・年収600万円の40代独身の上限は3000万円!?
- ・年収700万円の共働き夫婦の上限は5000万円!?
- ・年収800万円の3人家族の上限は4500万円!?
- ・年収1000万円の30代4人家族の上限は5000万円!?
- ・年収1000万円の40代4人家族の上限は3500万円!?
- ・年収1000万円の50代夫婦の上限は3000万円!?
※サイト内の金利はすべて年率で表示







 関連記事
関連記事

プロの評判・口コミ
淡河範明さん
SBI新生銀行の住宅ローンは、10年固定、15年固定、20年固定といった金利が低い点が特徴です。
商品も特徴的で、介護状態を保障する団信や、長く借りていると金利が下がっていく「ステップダウン金利」があるのも主要銀行ではここだけです。
審査はオーソドックスに行なっている感じです。住宅ローン処理センターで集中審査しているので、窓口のかたの力量があまり問われず、公平に審査されるという印象です。
なお、相談から審査、契約の手続きまでネットで完結できるようになりました。不安な方には、ビデオ通話で自宅から気軽に相談ができるので、コロナ禍の現状では最適な方法が用意されているようです。