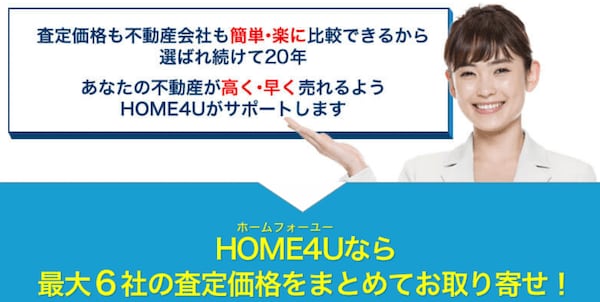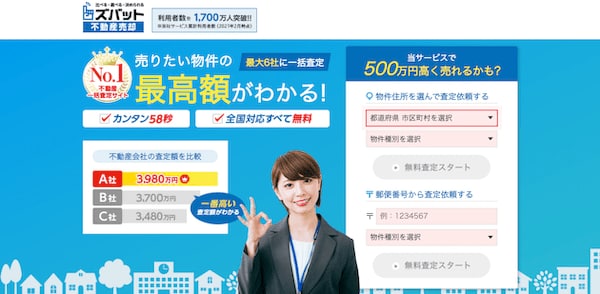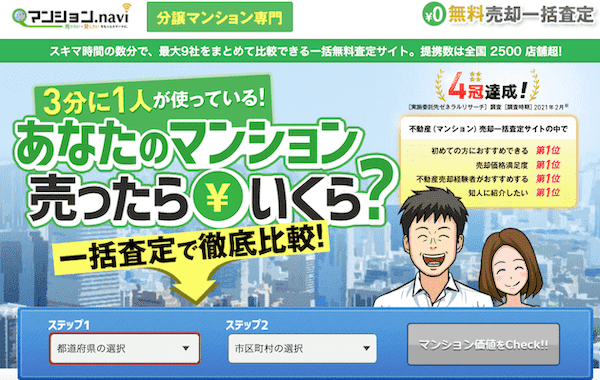築30年以上が経過した築古と呼ばれる中古マンションで特に気になるのが、管理費、修繕積立金の滞納金の有無と建て替えの問題です。特にマンション全体が抱える多額の滞納金は、将来のマンション維持に支障を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
希望の住戸に管理費、修繕積立金の滞納金がないかを確認!
中古マンションの購入時に、まず必ず押さえておきたいのが、滞納金の額です。毎月支払うべき管理費や修繕積立金が何らかの理由で支払われないままになっているのが、滞納金です。
注意したいのが、部屋の売り主が管理費や修繕積立金を払っていないにもかかわらず、そのような滞納金がある状態で売りに出される住戸があるということです。
不動産会社が契約に関する重要事項を消費者に説明する「重要事項説明」の段階で滞納金があればその金額も説明されますが、その時点では遅すぎます。
そのままでは、買い主側が売り主の滞納金の支払い義務を引き継ぐことになってしまいます。そうならないためにも、中古マンションを購入する場合は、早い時期に購入を検討している部屋の滞納の有無を確認しておきましょう。
もし、滞納金があれば、売却までに売り主側に支払ってもらうように確約してもらいます。あるいは、売却価格を下げてもらって、中古マンション購入後にその分をこちらで払うという方法もあります。
売却価格は変わらないのに、購入後に滞納金を支払うことにならないよう、契約前に仲介をする不動産会社にしっかり依頼しましょう。また、決まった内容は、契約書に明記したいものです。
【関連記事はこちら】>>修繕積立金の相場は?安い新築マンションには要注意!?
管理会社は滞納者に一定期間催促するだけ
管理会社が、滞納金を徴収する義務を負うものと思っている人は少なくないようです。しかし、管理組合が管理会社に委託した業務内容を記した「管理委託契約書」では、多くの場合、支払いが遅れている人に、管理会社が催促する期間や方法が定められているにすぎません。
その期間は管理会社と管理組合との契約に基づき、通常3カ月から半年程度となっています。これは管理の責任は、管理組合(所有者たちで作った組合)
■高額な一時金が必要になることも
滞納金が多いと、さまざまな問題が生じます。たとえば、早急に修繕をしなければならないくらい建物が古くなっているなら、各世帯から「一時金」として、数十万円単位のお金を徴収せざるを得ないことがあります。
これまでにも中古マンションを購入し、居住後数年して数十万円の一時金を負担させられたという例があります。滞納者への強い催促を行ってこなかった管理組合と理事会のツケを、新規に購入した人が払うことになるのです。
ただ、滞納している人が全くいないという中古マンションは少ないので、マンションに滞納金があるというだけで購入を控える必要はありません。ですが、金額が膨らんでいれば、管理体制に問題がある可能性があることを頭に入れておきましょう。
■滞納金は5年で時効が成立する?!
滞納金の支払いをめぐっては、20年近く前に最高裁で判決が出ました。このとき「マンションの滞納管理費は5年で時効」となりました。その際の裁判では、総額173万9920円のうち、5年以上過ぎた104万200円は時効と判断されたのです。最高裁の判断ですから、判例となりました。これにより、5年を超えた分は回収できなくなりました。
2020年4月1日から改正民法が施行されましたが、それでも管理費や修繕積立金の時効は5年と考えられており、大きな変化はないようです。
マンション全体の滞納金も必ず確認すること

「自分の部屋に滞納金がないから」といって安心はできません。マンション全体に多額の滞納金があるケースもあります。
多額の滞納金があると、予定通り修繕ができず、マンションの維持管理が適切に行われなくなる可能性があります。マンション全体の滞納金額は、重要事項説明で告げられますが、その段階で情報を得るのは遅いのです。
中古マンションの購入を検討している場合、早めに不動産会社に尋ねましょう。できる限り、直前の決算期の額を教えてもらうようにします。
過去には、マンション全体で多額の滞納金がある住戸を仲介した不動産会社が、調査を怠り、そのことを買い主側に説明しなかったとして、買い主側が、仲介した会社を訴えた例がありました。買い主側は、多額の滞納によりマンションの資産価値が大幅に下落するはずとして、説明があれば購入しなかったと主張しました。
最終的に仲介した会社が手数料を返して、和解となりましたが、買い主側からすると、このために使った時間と精神的な負担は相当大きいものだったはずです。
旧耐震マンションの建て替えには有利な制度も

築古マンションの場合、もう一つ気になるのが建て替えの問題です。
築30年~40年頃になると、建て替えの話が出てくるマンションがあります。きちんと管理をしていけば、コンクリート自体はまだ十分、維持できます。ただ、設備などが古くなり、不便を感じるという意見が上がってくるようになるのです。
また、1981年6月以前に建築確認を受けたマンションのほとんどが旧耐震基準で建築されていますので、大地震が到来する可能性を考えて、建て替えようという話が出てくることもあります。
旧耐震基準で建てられたマンションの建て替えを促すため、容積率の割り増しを行う制度があります(詳しくは、「国土交通省:容積率の緩和特例について」参照)。
容積率とは、「敷地面積に対する総床面積の割合」のことで、%で表されます。容積率200%といえば敷地面積に対して2倍の総床面積を持つ建物が建てられます。1000㎡の敷地があれば、建物の総床面積は2000㎡が上限ということになります。
容積率の数値は都市計画によって定められていますが、老朽化した分譲マンションの建て替えを促進するため、旧耐震基準の建物についてこの容積率が緩和されます。
マンションの容積率に余裕があれば、その分を利用して建て替え後の住戸を増やすことができるということになります。増えた住戸を売却すれば、建築費の一部を賄うことができ、住んでいる人の負担も減らせます。過去にはこういった手法で、建て替えを実施した事例が見られました。
建て替えの実施例はわずか
ただ、実際にマンションの建て替えを行うには、区分所有者と議決権の5分の4以上の賛成が必要で、その道のりは簡単ではありません。
国土交通省の調査によれば、2020年4月時点でマンションの建て替えは、建て替え決議などの実施準備中も含めて、全国でわずか295件(被災マンションは除外)でした。実際、建て替えには、合意形成を図るために非常に時間がかかります。住み慣れた住戸から離れたくない人にどう対応するか、借り住まい費用を負担しづらい人にどう対応するか、など問題が山積しているからです。
しかも、近年の建て替え事例では、戸当たりの負担額が増えています。負担金があるなら建て替えには反対だという話は少なくありません。2012年~2016年に竣工したマンションでは、負担金の平均は戸当たり約1100万円にのぼっています。
実際の建て替えが行われたケースでも、高齢になって1千万円を超える金額を支払った上に、部屋が狭くなったり、負担金が支払えずに区分所有権を売却し、遠方に引っ越しせざるをえなかったりした人も出ています。
購入しようとする中古マンションが築20年以内であれば、まだ建て替えは検討に上がっていないでしょう。ですが、居住後10年、15年とたつにつれ、そういった話が持ち上がってくるかもしれません。住んでみると時間の流れはあっという間です。
築古の中古マンションは、滞納金の有無や建て替えについて調べよう
築古のマンションを購入する際には、管理費や修繕費の滞納金はないか、建て替えの話が出ているのか、あるいは将来的に建て替えの話が起きる可能性があるかなどを調べる必要があります。
新築マンションを選ぶ以上に長期的な視野にたって物件選びをすることが大切になるでしょう。
【関連記事はこちら】>>ヴィンテージマンション価格ランキング・ベスト10 あなたのマンションの相場、値上がり率は?
- 「マンション購入前の注意点」記事一覧
-
【新築マンション購入前の注意点】
1.新築マンションは「青田売り」が主流な理由
2.購入後に後悔しない「現地見学」のポイント
3.「定期借地権付きマンション」のメリット・デメリット
4.「地権者住戸」が多い物件にはどんな問題がある?
5.「管理組合」と「管理会社」の違いとは
6.購入後に不動産会社が倒産したらどうなる?
7.「専有部」と「共用部」の違いを知っておこう
8.「高層階」と「低層階」のメリット・デメリット
9.新築マンションの「価格」を決定する要素は?
10.「売れ残り住戸」が大量に発生するとどうなる?
11.マンションの注文住宅「コーポラティブハウス」とは
12.「耐震」「制震」「免震」、ハイブリッド型の「免震&制震」って何?
13.マンション遮音の基本
【中古マンション購入前の注意点】
1.中古マンションのメリットや注意点
2.中古マンション見学のポイント
3.中古マンションの登記簿の見方
4.中古マンション管理契約とは?
東京そのほか
| おすすめ記事はこちら 【購入】中古マンションを選ぶ際の注意点 【購入】物件見学時のポイント 【購入】登記簿に関する注意点 【売却】不動産一括査定サイト33社比較 【売却】マンションを高く売る方法 【売却】マンション売却の税金 |
| ◆SUUMO(スーモ)売却査定 | |
| 特徴 | ・圧倒的な知名度を誇るSUUMOによる一括査定サービス ・主要大手不動産会社から地元に強い不動産会社まで2000社以上が登録 ・電話番号の登録は任意なのでしつこい営業電話を避けられる |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地 |
| 紹介会社数 | 10社(主要一括査定サイトで最多) |
| 運営会社 | 株式会社リクルート住まいカンパニー(東証プライム子会社) |
|
|
|
|
|
|
| ◆HOME4U(ホームフォーユー) | |
| 特徴 | ・悪質な不動産会社はパトロールにより排除している ・20年以上の運営歴があり信頼性が高い ・1800社の登録会社から最大6社の査定が無料で受け取れる |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、ビル、アパート、店舗・事務所 |
| 紹介会社数 | 最大6社 |
| 運営会社 | NTTデータ・スマートソーシング(東証プライム子会社) |
|
|
|
|
|
|
| ◆ズバット不動産売却 | |
| 特徴 | ・厳選した不動産会社のみと提携 ・比較サイト運営歴20年以上の会社が運営 ・情報セキュリティマネジメントシステムの国際認証基準である「ISO27001」の認証を取得しており安心感あり |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション、一棟ビル |
| 紹介会社数 | 最大6社 |
| 運営会社 | ウェブクルー |
|
|
|
| ◆イエウール | |
| 特徴 |
・掲載企業一覧を掲載、各社のアピールポイントも閲覧可能 |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地 |
| 紹介会社数 | 最大6社 |
| 運営会社 | Speee |
|
|
|
|
|
|
| ◆LIFULL HOME'S(ライフルホームズ) | |
| 特徴 |
・日本最大級の不動産ポータルサイト「LIFULL HOME'S」が運営 |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、倉庫・工場、投資用物件 |
| 紹介会社数 | 最大6社 |
| 運営会社 | LIFULL(東証プライム) |
|
|
|
|
|
|
| ◆マンションナビ | |
| 特徴 |
・マンションの売却に特化 |
|---|---|
| 対応物件 | マンション |
| 紹介会社数 | 最大9社(売却・買取6社、賃貸3社) |
| 運営会社 | マンションリサーチ |
|
|
|
|
|
|
| ◆いえカツLIFE | |
| 特徴 |
・対応可能な不動産の種類がトップクラス ・共有持ち分でも相談可能 |
|---|---|
| 対応物件 | 分譲マンション、一戸建て、土地、一棟アパート・マンション・ビル、投資マンション、区分所有ビル(1室)、店舗、工場、倉庫、農地、再建築不可物件、借地権、底地権 |
| 紹介会社数 | 最大6社(売買2社、買取2社、リースバック2社) |
| 運営会社 | サムライ・アドウェイズ(上場子会社) |
|
|
|
|
|
|
一括査定サイトと合わせて
利用したい査定サイト!
| ◆ソニーグループの「SRE不動産」売却査定 | |
| 特徴 | ・両手仲介・囲い込みを行わない ・上場企業のソニーグループが運営 ・売却専門の担当者がマンツーマンで高値売却を追求 |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地(建物付きを含む)、収益用不動産 |
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県 |
| 運営会社 | SREホールディングス株式会社(ソニーグループ) |
|
|
|
| ◆中古マンション相場と10年後の価格を予想!【不動産価格データベース】 |